ニュースなどで百日咳の流行を見聞きして心配になっているパパ、ママも多いのではないでしょうか?
長引く咳に不安も募ると思います。
感染力が非常に強い百日咳ですが、どんな症状が出るのでしょうか?気をつけたいポイントをまとめました。
百日咳とは?
1906年に報告された百日咳は主に百日咳菌が原因で、けいれん性の咳発作を特徴とする感染力が強い急性気道感染症です。
百日咳に特徴的な激しい咳が100日ほど続くため“百日咳”という名前がつけられました。
百日咳は母体からの免疫(経胎盤移行抗体)が十分に移行しないため、乳児期早期の赤ちゃんから感染する可能性がある病気です。
とくに生後6か月以下で罹患すると重症化することがあり、肺炎や脳症などの合併症を併発して命を落とす危険性も高いとされるため注意が必要です。
主な症状
百日咳の経過は3期に分けられ、2〜3か月かけて回復していくとされます。
それぞれの期間にみられる特徴的な症状をみていきましょう。
① カタル期
乾いた軽い咳やくしゃみ、鼻水、微熱などの風邪症状から始まり、徐々に咳の回数も増えて強くなっていきます。
カタル期は2週間ほど続き、最も感染力が強い期間です。
咳が長引いているときは悪化する前に受診、早期診断してもらい治療を開始できるとよいでしょう。
② 痙咳期(咳発作期)
痙咳期は熱がないことが多く、カタル期の軽い咳が徐々に変化していきます。
スタッカートと呼ばれる乾いた短い咳(百日咳に特徴的なけいれん性の咳=痙咳)が「こんこんこん…」と続き、そのあと息を吸い込むときにフーピングと呼ばれる「ヒューー」という笛を吹くような音が聞こえます。
この「こんこんこん、ヒューー」という百日咳に特徴的な咳発作を“レプリーゼ”といいます。
痙咳期のレプリーゼの発作は2〜3週間ほど続き、とくに夜間に症状が悪化し眠れなかったり咳こみ嘔吐をすることもあります。
激しい咳をするため顔が赤くなったり息が苦しくなります。
息を詰めて咳を繰り返すため顔の静脈の圧があがり血管が破裂して顔が浮腫んだり、鼻血、目の周りなどに点状出血(赤い小さな斑点)、眼球結膜出血(白目の部分に出血)が起こることもあります。
乳児期早期の小さな赤ちゃんでは特徴的な咳がなく、息を止めているような無呼吸発作→チアノーゼ(顔色や唇の色や爪の色が紫色になる)→けいれん→呼吸停止と経過することもあるので咳の有無に関わらず注意して観察する必要があります。
③ 回復期
激しい咳は2〜3週間かけて落ち着いてきますが、咳が完全になくなるには数週間〜数か月かかることもあります。
とくに大人は特徴的な咳を示さないものの長引くことがあり、冷たい空気を吸い込むなどの刺激により咳発作がでることがあります。
百日咳の特徴
病気の経過に伴い変化していく咳
主な症状で説明した通り、軽い咳→スタッカート(短く連続した咳)+フーピング(息を吸い込む音)=レプリーゼ→徐々に軽快していく咳と数か月かけて変化していきます。
流行する時期
百日咳は季節に関係なく1年中いつでも発生する可能性があります。
近年は春から初夏にかけて、4〜6月あたりに流行し始め夏頃にピークを迎える傾向にあります。
しかし2025年は例年より早く流行が始まり、4月の上旬には過去最多の患者数が記録されました。
5月現在も全国の多くの都道府県で感染者数が増加しています。
潜伏期間
感染してから発症するまでの期間は5〜10日ほど(最大3週間)です。
かぜのような症状で始まりますが、咳の出始めから2週間ほど(カタル期)はとくに感染力が強いため人に移してしまう可能性が高いです。
感染経路
① 飛沫感染
→咳やくしゃみ、会話により口から飛び散るしぶきを浴びてウイルスを吸い込んで感染する
② 接触感染
→直接の接触、ウイルスが付着した物(おもちゃなど)を触ったり舐めて感染する
百日咳は感染力がとても強く、家族内や保育園・学校内などでの集団感染が起こりやすいとされています。
ワクチン接種や手洗い・うがいの徹底、風邪症状があるときはマスクをするなど、うつらない・うつさない感染対策が大切です。
何度も繰り返し感染する
百日咳は感染を経験しても終生免疫は獲得されないので何度も繰り返し感染します。
検査
子どもの場合は特徴的な症状(咳や咳こみ嘔吐)を認めると臨床診断がおり、検査をすることで確定診断につなげます。
RSウイルスやインフルエンザの検査と同じように細い綿棒を鼻に入れ、ぬぐい液を使用した迅速診断キットで検査します。
結果がでるまで2〜3日かかります。
他にも血液検査による抗体測定などでも診断がつくこともありますが、ワクチンの接種歴や菌の量が少ないときには診断が難しいこともあります。
とくに大人は他の疾患との区別が必要であり、咳の期間は長くても症状が軽いと風邪との区別がつきにくく、気づかないうちに周囲に感染させてしまっていることもあります。
治療
百日咳菌に有効な抗菌薬での治療と咳止めの薬などの対症療法を行います。
症状がでてから早い段階で抗菌薬を使用するととくに有効なので、長引く気になる咳があるときは早めに受診するのがよいでしょう。
6か月未満の赤ちゃんで呼吸困難の症状が強い場合や嘔吐を繰り返すなどの場合には、入院して治療が必要になることもあります。
予防注射
2024年度以降、5種混合ワクチン(ポリオ、百日せき、破傷風、ヒトインフルエンザ菌感染症=Hib感染症、ジフテリア)を主に用いることとしています。
日本小児科学会は生後2か月頃から期間をあけながら4回接種することを推奨しています。
百日咳抗体価が10歳未満で低下することから学童期以降の百日咳予防のため、5回目の予防注射として2種混合ワクチンか3種混合ワクチンを追加接種することも推奨されています。
詳しくはかかりつけのお医者さんと相談しながら予防注射を進めていきましょう。
感染対策
まずは予防注射を確実に受けましょう。
百日咳は飛沫感染と接触感染です。
こまめな手洗いうがいが大切です。
とくに指の間や指先は洗い残しが多いので意識して石鹸で丁寧に洗いましょう。
子どもが小さくて手洗いが大変なときはお手拭きやウエットシートで拭いたりアルコール消毒液を活用しましょう。
咳などの風邪症状があるときはマスクを着用したり外出自粛をするなど周囲へ感染させないようにしましょう。
とくに乳幼児は重症化のリスクがあるためパパ、ママをはじめとする周囲の大人が感染源とならないよう気をつけましょう。
急いで受診したほうがいいとき
息継ぎもできないほど激しい咳をしていたり呼吸を止めてしまっているときは迷いなく救急車を要請します。
2週間以上の咳があったり、咳こみ嘔吐がある激しい咳のときも早めに受診を検討してくださいね。
他の病気との区別をつけ、早期に治療開始することが望ましいです。
いつから登園・登校できるの?
百日咳は感染症予防のため学校保健安全法により出席の停止が求められている病気です。
学校保健安全法施行規則の第十八条の二において百日咳は第二種の感染症と位置づけられていて、同法の十九条 ロ『百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。』と出席停止期間の基準が定められています。
つまり
・特有の咳がなくなるまで
・または5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで
は欠席しなくてはなりません。
このどちらかを満たしていれば登園・登校はしても大丈夫ということになりますが、咳が続いていて苦しいときなどは無理せずに体調を回復させてから登園・登校の再開をしましょう。
通っている園によっては登園許可証の提出が求められることもあるので事前に確認しましょう。
大人も感染する?
大人も感染する可能性があります。
子どもの頃に予防注射をしていても効果が薄れていってしまい、感染するリスクがあがります。
しかし大人は子どものように重症化しないことも多く、他の風邪などと間違えられやすいため放置してしまうこともあるでしょう。
子どもや周囲の人に感染させてしまうこともあるので、風邪症状があるときはマスクをするなど感染対策を行い、病院を受診しましょう。
まとめ
百日咳の名の通り元気に回復するまで時間がかかるため、体力が奪われ、看病疲れも出てしまい親子ともに消耗する数か月を過ごす覚悟が必要な病気です。
子どもも大人も「ただの風邪…」などと思わず、流行している時期だからこそ早めの受診をして適切な治療につなげていきましょう。


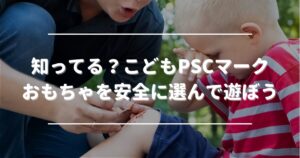


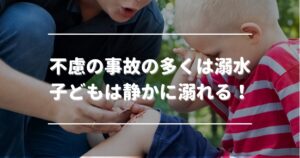

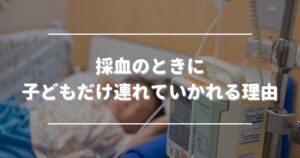

コメント