秋の味覚といえばどんなものを思い浮かべますか?
甘くてジューシーなぶどうなどの丸くてつるっとした食材は誤嚥に注意!
過去の事例を振り返りながら、安全に食べる方法やおすすめグッズを紹介します。
ぶどうを丸ごと食べて誤嚥!通行人に助けられた事例
ぶどうを丸いまま食べてしまい誤嚥、入院治療を要した事例を見てみましょう。
年齢:2歳6か月
性別:男の子
場所:自宅の食卓
時間:18:40頃
状況:直径3cm程度のぶどう(皮剥き済み、種なし)を丸ごと初めて食べた。突然咳き込み始め、泡を吹いて意識を失ったため、誤嚥を疑って母親が手で掻き出そうとしたが出てこなかったため救急要請をした。救急車を待つため男の子を抱いて玄関先に出たところ、通りがかりの通行人にハイムリッヒ法(腹部突き上げ法)をしてもらったところぶどうの塊が排出され泣き始めた。病院へ搬送後にチアノーゼ、酸素化不良、傾眠傾向を認めたため入院。ぶどう誤嚥による上気道閉塞の解除後の陰圧性肺水腫の合併と診断され、入院治療を行い6日後に退院した。後遺症はなかった。
(日本小児科学会雑誌2014年6月号掲載 日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会 傷害注意報より抜粋)
今回の事例はぶどうを丸ごと食べて誤嚥してしまいましたが、たまたま通った通行人による応急処置で後遺症を残さなかったケースでした。
男の子が合併した陰圧性肺水腫とは、のどが詰まったり気道が塞がったときに強い力で吸おうとする→肺の圧が下がる→血管から水分が肺にしみ出す→肺に水が溜まって苦しくなってしまう状態のこと。
食べ物の誤嚥だけでなく、嘔吐物の誤嚥やいびき・無呼吸で起こることもある症状です。
救命できずに亡くなる事例もある
先の紹介したぶどうの誤嚥は通行人のおかげで奇跡的に助かりましたが、残念ながら救命できずに亡くなってしまう事例もたくさんあります。
ショッキングな内容も含まれていますが、子どもの安全のために知っておきたいパパ、ママは読んでみてください。
① こんにゃく入りゼリーを歩きながら食べて誤飲した事例
② 目を離した隙に固めのパンを丸ごと口に詰め込んで食べた事例
どちらも子育てをしていると「あるある」な場面ではないかと思います。
ヒヤリ…と心当たりのあるパパ、ママもいるかもしれません。
窒息してから5分以内の行動がカギ
食べ物やおもちゃを誤飲、窒息してから数分で脳障害が発生するリスクがあります。
とくに救命率を大きく分けるのが窒息してからの5分間。
窒息してから3〜4分で顔が青紫色になり始め、5〜6分で呼吸停止や意識消失、10分で脳障害、15分以上経過すると脳死状態に至るとされています。
そのため1秒でも早い救急要請が大切になります。
パパ、ママ自身で頑張って助けようと思っても上手くいかずに時間だけが過ぎてしまい手遅れになってしまうこともあるかもしれません。
まずは119番、その後に救急隊の指示に従って応急処置をしながら救急車の到着を待ちましょう。
丸くてつやつやの食材は小さく切る
事例にもあったように丸くてつやつやのぶどうやミニトマト、いちご、うずらの卵などの食材は1/4カットしてあげることはもちろん、丸くない形にすることが大切です。
おしゃべりしたり笑ったり、咳が出そうで息を吸ったり、そんなときに丸っこい形だと勢いよく吸い込んでチュルンと入ってしまうリスクがあがります。
でも1つずつ1/4カットは大変!そんなときに役立つ便利グッズはこちら!
食材を挟んでギュッと握るだけで1/4サイズに切れます。
しかも丸洗いできるので衛生面も◎
子どもの食事だけでなく、パパ、ママのサラダ作りなど普段のお料理でも使えて1つ持っていると便利ですね。
何歳まで小さくカットを続ける?
何歳になるまで続けるかという明確な基準はありません。
子どもの食べる力や意欲に合わせて対応していく必要があります。
ただし大きくなるまでずっと1口カットを続けるのもあまりよくありません。
というのも子どもは自分で大きな食べ物を前歯でかじりとって、1口サイズを学んでいきます。
おにぎりなどはあえて大きく作り、自分でかじる練習をしていきましょう。
その際は必ずごっくんと飲み込むまで目の前で見守りましょう。
2015年や2024年には小学1年生が給食で提供されたうずらの卵を喉に詰まらせ窒息、死亡した事例もあります。
この時期は乳歯が永久歯に生え変わる時期とも重なるため、大きくなったからといって安心はできません。
同時に食事中に大きな声でしゃべらない、ふざけないなどマナーの部分も一緒に伝え、安全においしく食事をする力を育んでいきたいですね。
まとめ
旬の食べ物はおいしく栄養価も高くなるので本来は積極的に摂っていきたいもの。
お腹が空きすぎてがっつくように食べるときや、眠たくてうとうとしているときは無理に食べると危険があるので別の機会に。
過度に怖がらず、安全に食べられるよう工夫と見守りをしながら秋の味覚を楽しみましょう。



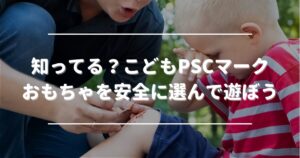

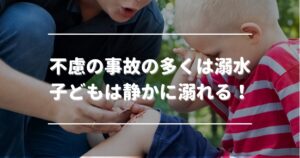



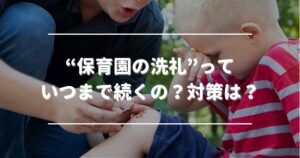
コメント