子どもはよく風邪をひきますが、ちょっとした熱や咳、鼻水から始まったと思ったらどんどん苦しそうになって症状が酷くなってきた…そんなときはRSウイルス感染症が疑われることがあります。
RSってよく聞くけど、実際どんな病気なのか徹底解説します!
RSウイルス感染症とは?
RSウイルスとは正式にはRespiratory syncytial virus(レスピラトリー・シンシチアル・ウイルス)の頭文字をとったもので、略して“RSV”と呼ばれることもあります。
RSウイルスは大きく分けてA型とB型の2種類が存在していて、一般にA型のほうが重症になるといわれています。
A型とB型は1年ごとに交互に流行するとされていますが、今年はどの型が流行しているのかまでは把握されていません。
主な症状
鼻水、鼻づまり
水のような鼻水や鼻づまりといった軽い鼻風邪のような症状から始まり、徐々に白っぽく粘り気のある固い鼻水になっていきます。
常に鼻水がたれている状態なのでこまめに拭き取りをするか、必要なときは吸引器で吸ってあげましょう。
感染を繰り返している小学生以上の子どもや大人の場合は軽い鼻風邪程度で治ることが多いです。
咳
コンコンという強い咳やむせるような咳が出ます。
悪化するとゼイゼイ、ヒューヒューというような喘鳴が聞かれることもあります。
むせこんでしまい母乳やミルクが飲みにくくなってしまったり、水分や食事がとれてもむせて吐いてしまうことも。
気管へのダメージが大きいため、症状のピークを超えたあとも2〜3週間ほど咳が長引くことがあります。
2歳頃になると気管支炎(呼吸困難がない痰がらみの咳)だけで済む場合もあります。
呼吸困難(多呼吸、陥没呼吸)
普段より呼吸の回数が増えたり、鎖骨の上の部分やみぞおち、肋骨の1番下の部分が呼吸に合わせてペコペコへこむ陥没呼吸があるときは呼吸困難を起こしているサインです。
苦しくなると呼吸をお休みして突然死につながることもあるため、夜間であっても救急車を呼んで一刻も早く病院を受診しましょう。
熱、倦怠感
38〜39℃の高熱が出ることも、とくに熱が出ないこともあります。
倦怠感によるぐったりと元気のなさもみられます。
声枯れ、喉の痛み
長引く咳により声枯れや喉の痛みがでます。
喉の痛みで食欲の低下や水分が摂れないことで脱水症状がみられることもあります。
下気道炎(細気管支炎、肺炎)
RSウイルスに感染した子どものうち約70%は咳や鼻水の上気道炎の症状のみで治っていきますが、残りの約30%は細気管支炎や肺炎などの下気道炎を起こして重症化します。
吸った空気は太い気管支を通って細い気管支に送られていきますが、この細い気管支に炎症が起こり粘膜が腫れて呼吸がしにくくなる状態が細気管支炎です。
呼吸困難による顔色の悪さ、唇の色が青紫になる、ゼイゼイ、ヒューヒューの音が酷くなる、苦しくて小鼻がぴくぴくする、呼吸の回数が増える、肩で息をする様子があれば細気管支炎や肺炎を起こしている可能性があるので急いで受診する必要があり、入院での治療を要することがあります。
RSウイルス感染症の特徴
数日かけて重症化する
最初は軽い風邪症状ですが、だんだん症状が重くなっていき発症後3〜5日後にピークをむかえることが多いのが特徴です。
ピークを超すと1〜2週間かけて回復していきますが、生後6か月未満の赤ちゃんや低出生体重児、心臓や肺などに基礎疾患がある子どもはとくに重症化しやすく、入院して治療が必要なことがあります。
喘息を発症しやすくなる
スウェーデンの研究でRSウイルスに感染して入院した経験がある子どもとそうではない子どもを比べたときに、喘息の発症率が高くなったという報告があります。
これはRSウイルスの感染により気道の過敏性を引き起こしたり、もともと喘息になりやすい体質の子どもが感染を引き金に喘息を発症するからだと考えられています。
流行する時期
もともとは秋〜冬にかけて流行するウイルスでしたが、近年は夏から増加傾向で秋にピークをむかえています。
しかし2021年以降は春〜初夏に増加傾向で夏にピークをむかえるなど流行のタイミングがどんどん早まっていて、年中を通して感染の可能性があります。
まもなく流行する時期にさしかかるため、今後の流行状況を注意して見ていく必要があります。
潜伏期間
感染してから発症するまでの期間は4〜6日ほどです。
ウイルスの排泄期間は7〜21日と長いため集団生活のなかでとくに感染が広がりやすいです。
感染経路
① 飛沫感染
→咳やくしゃみ、会話により口から飛び散るしぶきを浴びてウイルスを吸い込んで感染する
② 接触感染
→直接の接触、ウイルスが付着した物(おもちゃなど)を触ったり舐めて感染する
そのため保育園や幼稚園などで集団発生することが多いです。
クラスや園で流行していないか確認し、流行しているときや子どもに少しでも風邪症状があるときはマスクをするなど、うつらない・うつさない感染対策が大切です。
何度も繰り返し感染する
RSウイルスは1歳までに半数以上、2歳までにほぼ全ての子どもが感染を経験するといわれています。
RSウイルスは200種類ある風邪ウイルスの1つのため風邪の一種ですが、他のウイルスが起こす風邪と違って重症化するおそれのあるウイルスで、終生免疫は獲得されないので他の風邪と同じように何度も繰り返し感染します。
多くは数日ほどで回復していきますが、初回感染時により重症化しやすいといわれています。
検査
インフルエンザやヒトメタニューもウイルス感染症の検査と同じように細い綿棒を鼻に入れ、ぬぐい液を使用した迅速診断キットで検査します。
15分程度で結果がでます。
RSウイルスの検査は1歳未満の赤ちゃんか入院の必要がある子どもにしか保険適応されていないので、症状や周囲の流行状況によって診断されたり、医療機関が負担して検査が行われています。
治療
特効薬がないため年齢や症状に合わせ対症療法をします。
水分や栄養をしっかりとり、温かくしてゆっくり休むことが治療になります。
咳や鼻水を抑える薬や痰切りの薬、熱を下げる薬などが処方されることがあります。
症状が強くて入院になる場合は点滴や酸素投与をして治療し、呼吸状態が悪くなると人工呼吸器をつけて呼吸のサポートをすることもあります。
予防注射
シナジスやベイフォータスはRSウイルスが体内で増殖することを防ぎ、重篤な下気道炎の発症を抑える抗RSウイルス薬で、保険適用で接種できます。
シナジスはRSウイルス感染症が流行する前の時期から月1回の筋肉注射を継続します。
しかしこれは子ども全員が対象ではなく、低出生体重児や心疾患、呼吸器疾患、免疫不全、ダウン症候群などの基礎疾患のある子どもが対象です。
シナジスを注射してもRSウイルスの感染を完全に予防することはできず、あくまでも重症化を抑制するものです。
ベイフォータスは全ての子どもに適応されましたが保険適用外で自費での任意接種のため、とても高額です(新車が買えるくらいの金額です…)。
感染対策
RSウイルスは飛沫感染と接触感染です。
重症化のリスクが高い1歳未満の赤ちゃんにいかに感染させないようにするかが重要です。
大人も子どもも風邪気味の人は赤ちゃんとの接触をできるだけ減らしましょう。
風邪をひかないように家族全員でこまめな手洗いうがいをすることも大切です。
とくに指の間や指先は洗い残しが多いので意識して石鹸で丁寧に洗いましょう。
子どもが小さくて手洗いが大変なときはお手拭きやウエットシートで拭くとよいでしょう。
RSウイルスにはアルコール消毒が有効です。
家族内で風邪気味の人やRSウイルスに感染している人がいるときは、ドアノブなどの触れる場所やおもちゃなどをアルコール消毒すると接触感染予防になります。
花粉も飛び始めますが、換気も忘れずに。
コップやタオルの共用をやめることも大切です。
バランスよく食べてよく寝る規則正しい生活を送って、免疫力を高めてRSウイルスに負けないように過ごしましょう。
急いで受診したほうがいいとき
こんなときは急いで受診しましょう。
① 咳が酷くなる、ゼイゼイ、ヒューヒューの喘鳴がでる
② 呼吸が早い・多い、呼吸が苦しそう、肩で呼吸している、小鼻がぴくぴくする
③ 鎖骨の上の部分・みぞおち・肋骨の1番下の部分が呼吸に合わせてペコペコへこんでいる
④ 食事、水分がとれない
⑤ 急にぐったりする
⑥ 顔や唇の色が青紫になる(チアノーゼ)
⑦ 呼吸を止める(無呼吸)
RSウイルスは急に悪化することがあるため夜間でも急いで受診しましょう。
いつから登園・登校できるの?
RSウイルスは出席停止基準が定められていません。
そのため咳や熱が落ちついて全身の状態がよくなれば登園・登校できますが、通っている保育園や幼稚園の規定を確認しましょう。
感染力の強いウイルスのため、無理して登園・登校することは子ども自身が辛いのはもちろん、友だちや先生にうつしてしまうリスクがあるので慎重に判断しましょうね。
大人も感染する?
RSウイルスは大人も感染しますが健康な大人であれば感染しても軽症で済み、多くはちょっとした風邪のような症状で自然に治ります。
ただし高齢者や喘息・COPD・心疾患といった基礎疾患がある方や免疫機能が低下している方の場合は肺炎などを起こす可能性があります。
高齢者がRSウイルス感染症によって入院したり死亡にいたる事例もあるため、じーじ、ばーばと同居しているお家は子どもが体調不良のときはより注意が必要です。
まとめ
どんなに感染予防をしていても風邪はもらってしまうもの。
急激に症状が悪化している我が子を目の当たりにすると不安になってしまうと思いますが、しっかり病院を受診すれば大丈夫。
看病疲れのなか大量のウイルスに曝されながら近くでお世話をするパパ、ママも症状が重くなることもあるので、“ただの風邪”と思わずに気をつけましょうね。
万が一、入院することになってしまったときにはコチラの記事で持ち物をまとめているので参考にしてみてください。
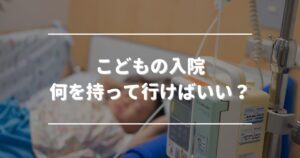


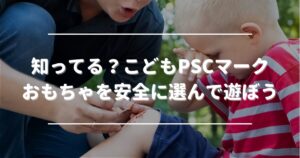


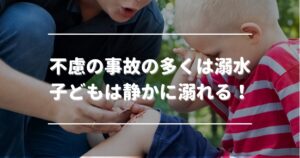



コメント