子どもが発熱する病気はたくさんありますが、長く続く高熱の原因として“川崎病”は頻度の高い病気です。
しっかり治療する必要がある病気で、とくに4歳以下の子どもによくみられるためパパ、ママには知っていてほしい病気の1つです。
今回は川崎病がどんな症状のある病気なのかをまとめました。
川崎病とは?
川崎病とは1967年に川崎富作先生が報告した原因不明の全身の血管炎です。
川崎病は発熱や首のリンパ節の腫れなどいくつかの症状がありますが、1番の問題は心臓の血管の一部である冠動脈にこぶのように膨らんだ瘤ができてしまうこと。
冠動脈瘤が大きくなってしまうと血栓(=血のかたまり)ができやすくなってしまい、将来的に狭心症や心筋梗塞を起こす危険が高まります。
大きな冠動脈瘤ができてしまうと後遺症として残りますが、急性期の治療が進歩したことによって適切な治療を受ければ後遺症のリスクは減りました。
必ず入院して点滴による治療が必要になります。
できるだけ早く熱をさげ、血管の炎症を抑えることが大切です。
主な症状
川崎病には特徴的な症状が6つあります。
それぞれみていきましょう。
① 5日以上続く発熱
38℃を超える高熱が5日以上続きます。
ときに数日で解熱してしまうこともありますが、発熱の期間が短くても川崎病と診断されればきちんと治療をする必要があるため、他の症状と合わせてみていく必要があります。
② 結膜の充血
白目の部分が充血します。
泣いたり目をこすったりしていなくても、ぱっと見てわかるくらいに赤い目をしているのが特徴です。
③ いちご舌、唇の赤み
川崎病の特徴的な症状として“いちご舌”と呼ばれる舌になることがあり、その名の通り、いちごのような赤くてブツブツした見た目の舌になります。
溶連菌感染症など別の病気でもいちご舌がみられることもありますが、その他の症状とも合わせて見逃さないようにしたい症状の1つです。
舌と同様に唇も赤くなることがありますが個人差があり、パパ、ママから見ていつもより赤い気がする?程度のときから唇が切れて血が出てしまうほどのこともあります。
唇や口の中の痛みから食事や水分が進まなくなることもあるので、小さく切ったり喉ごしがいいメニューにするなどの工夫が必要です。
脱水にならないよう、おしっこが出ているかも注意して見ていきましょう。
④ 不定形発疹
体幹や手足など全身のいたるところに大小さまざまなサイズの赤いブツブツや蕁麻疹のような赤い発疹がでます。
発疹や赤みは数日で消えてしまうこともあるため、後の診断の参考になるように写真を撮っておくとよいでしょう。
BCGの接種部位が赤くなったり、くじゅっとした水疱になることもありますがこれも川崎病の特徴の1つです。
いずれの赤みも痒みはないため、子どもが気にしない(痒がらない)発疹や赤みには要注意です。
⑤ 手足の赤み、むくみ
手足が赤くなったり、指で押しても跡や凹みの残らない“硬性浮腫”と呼ばれる症状がでることがあります。
血液中の成分(アルブミンなどのたんぱく質)が血管の外に漏れ出して浮腫を起こしているため、痛みがあることも。
痛くて不機嫌になったり、手足に触れられることを嫌がったりすることがあります。
⑥ 首のリンパ節が腫れる
“頸部リンパ節腫脹”といって、首の両側か片側にクルミ大くらいの腫れを感じることがあります。
触ったり押したりすると痛みを感じることがありますが、化膿はしません。
その他の症状:膜様落屑
川崎病の治療を行ったあとの回復期に“膜様落屑”といわれる手足の指の皮がべろんとめくれる症状があります。
指先と爪の間の皮膚からめくれ始め、手のひらや足の裏全体などまるっと一皮剥けてしまうこともありますが、それ以上に広がらないのが特徴です。
気にしてむしってしまうと血が出てしまうこともあるので注意して見てあげましょうね。
川崎病の特徴
乳幼児に多い
年間10000人以上の子どもが罹患し、そのうちの80〜85%が4歳以下の乳幼児が占めていて、患者数は年々増加傾向にあります。
6か月〜11か月の赤ちゃんが罹患率のピークを迎えますが、小学生以上の子どもでも発症することがあります。
稀ですが2回、3回と再発してしまうこともあります。
アジア人に多い
日本で初めて発見された川崎病は韓国、台湾などの東アジア圏で多く発症するとされています。
とくに日本は発症率が高い国の1つです。
2020年頃、コロナ禍の欧米諸国で新型コロナウイルスに感染した後の子どもに川崎病のような症状が現れたとニュースになりましたが、日本国内ではコロナ感染後における川崎病に似た症状の報告はされていないので、関連性は気にしなくて大丈夫そうです。
(むしろコロナ禍の日本では川崎病の患者数が平年より減少傾向でした。)
ずっと不機嫌
川崎病になると不機嫌になることが多いです。ちょっとグズる…ではなく、かなりの不機嫌。
高熱が続きしんどいこともそうですが、全身の血管に炎症が起こっている状態なので痛みや不快感を感じているのに言葉にできないストレスから不機嫌になっていると思われます。
普段の体調不良のときは熱がさがるタイミングで機嫌が戻ったりしますが、ずっとご機嫌ナナメのときは何か症状が出ていないか確認してみてくださいね。
潜伏期間
特定の病原体をきっかけに罹患するわけではないので、明確な潜伏期間はありません。
数日かけて症状がじわじわ出てきて、診断に至ることが多いです。
感染経路
何らかの細菌感染やウイルス感染、環境物質による刺激などが原因といわれていますが、明確な原因は特定されていないため感染経路も不明です。
同じような地域や時期に川崎病に罹患する子どもが増えるともいわれていますが、こちらも原因は不明です。
そのため川崎病にならないように対策するのは不可能でしょう。
しかし風邪やインフルエンザのように人から人へうつるものではないので、きょうだいや身近なお友だちが川崎病になっても心配する必要はありません。
遺伝するの?
川崎病は遺伝によって引き継がれるものではありません。
しかしパパ、ママ自身やきょうだいに川崎病になったことがある人がいる場合には一般の発症率よりわずかに高い傾向があるため、何らかの遺伝的要因が関与しているのではないかともいわれています。
川崎病は日本人をはじめとする東アジア系の人種での発症が多いと指摘されているので複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
検査
菌やウイルスが原因ではないので検査キットなどはありません。
症状のところであげた①発熱 ②目の充血 ③いちご舌 ④発疹 ⑤手足の浮腫 ⑥リンパ節の腫れ の6つの症状のうち5つ以上あるときに川崎病と診断されます。
症状が5つ以上揃わなくても、他の病気が否定されて川崎病を疑う症状がいくつかある場合には“不全型川崎病”と診断され、川崎病と同じ治療を進めていきます。
治療
なるべく早く診断して治療を始めたいので、その日のうちに緊急入院になります。
近隣のクリニックを受診したときは、入院設備が整っている近くの大きな病院を紹介してもらい、すぐに受診しましょう。
入院したら全身の血管の炎症を鎮めて冠動脈瘤ができるのを予防する薬を点滴で投与します。
同時に血が固まって血管に詰まるのを防ぐために血液をサラサラにする薬を内服します。
退院後も数か月は内服を続けます。
入院中は心臓のエコーを行い、冠動脈が拡大していないか(=瘤ができていないか)をチェックします。
退院後も約5年間は心臓のエコーを行うために通院が必要になります。
予防注射
特定の菌やウイルスが原因ではないので予防注射はありません。
感染対策
特定の菌やウイルスが原因ではないので人から人へ感染しません。
感染対策も不要です。
急いで受診したほうがいいとき
咳や鼻水など発熱に繋がりそうな症状がないのに高熱が続いたり、目や手足の赤みが気になるときは川崎病の可能性があるので早めの受診、治療に繋げましょう。
いつから登園・登校できるの?
感染症ではないので退院したらいつでも登園・登校できます。
しかし10日〜14日ほど入院生活を送るため、体力が落ちていることも考えられます。
子どもの様子を見ながらゆっくり集団生活へ戻っていきましょう。
大人も感染するの?
感染しません。
まとめ
症状や後遺症を知ると怖い病気のように思ってしまいますが、適切な治療を受ければ命にかかわることはほとんどありません。
そのためにも怪しいかな?と疑ったら早く病院を受診して治療を開始することが大切です。
パパ、ママ、子どもに関わる多くの方に知っていてほしい病気の1つでした。
素人判断は適切な治療に繋がらないこともあるので、気になったことは必ずかかりつけのお医者さんに相談してみてくださいね。


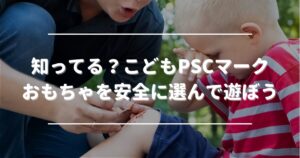


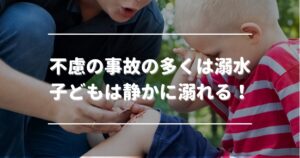

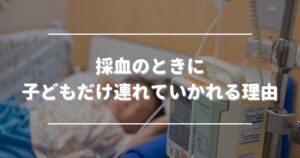

コメント