子どもの行動は時に大人の想像を超えるもの。
思わずヒヤッとした経験のあるパパ、ママも少なくないのでは?
そんな思いがけない事故から子どもを守る啓発のため、2025年7月14日から7月20日は“こどもの事故防止週間”です。
子どもの死因の多くは“不慮の事故”である
令和6(2024)年3月26日にこども家庭庁が発表した“こどもの不慮の事故の発生傾向と対策等”という資料を見てみましょう。
ここでは令和4(2022)年のデータですが、年間の子どもの死亡数の7.0%が不慮の事故が原因であるとされています。
0歳から14歳までの子どもを年齢別に分けた死因においても、全年齢の上位を不慮の事故が占めています。
不慮の事故の詳細では、0歳では窒息や誤嚥が、1歳以上では交通事故が上位にあがりますが、全年齢で共通しているのは溺水による水の事故。
小さなうちはお風呂での溺水、大きくなるにつれ海や川での溺水が多くなっていきます。
そこで国は関係省庁が連携して子どもの事故防止の取り組みを行えるよう、2016年に“こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議”を設置し、2023年からはこども家庭庁のもとで開催されています。
今年度のテーマは“水の事故防止”
毎年この夏休み目前の1週間が“こどもの事故防止週間”とされ、さまざまな啓発活動が行われています。
ここ数年はこの異常な暑さのこともあり“熱中症予防”や“車の置き去り事故予防”がテーマに扱われてきましたが、今年の7月14日から7月20日は4年ぶりに“水の事故防止”がテーマになりました。
子どもを水の事故から守るために気をつけること
子どもを水の事故から守るために気をつけたい4つのポイントとは?
① 子どもから目を離さない!
川や海でのレジャー時はもちろん、プールやお風呂でも必ず大人が目を離さないようにしましょう。
声をかければ聞こえる範囲にいる、ちょっと忘れ物をとりにそばを離れる…といった状況は子育て中ではよくあるシチュエーションですが、子どもが水の中にいるときは絶対にNG行動!
必ず近くで見守り、そばを離れる必要があるときは子どもを水からあげて一緒に行動してくださいね。
水の近くで待たせると、待ちきれなくて自分で入ってしまうこともあるのでやめましょう。
② 水が浅くても注意!
子どもは数cm、くるぶしくらいの水の浅さであっても溺れてしまいます。
とくに乳幼児は水が2.5cmあるだけでも溺れてしまうともいわれています。
庭のプールやお風呂での水遊びなど水を浅く張っているから大丈夫と思わずに、水のそばではいつ事故が起こってもおかしくないと危機管理能力を高めていきましょう。
③ 転落に注意!
魚釣りや磯遊びなど水に直接入らずに遊ぶ予定であっても、思わずバランスを崩してしまったり足を滑らせて水に落ちてしまうこともあるでしょう。
水に入る予定はなくてもライフジャケットを着用するなど、万が一の事故に備えた装備でお出かけしましょう!
大きな子どもだと遊び感覚で水に飛び込むチャレンジをしたくなると思いますが、河口で流れが激しかったり思ったよりも水が深くて足がつかなかったり…と自然の力の大きさには敵いません。
水の危険さをしっかり伝え、事前の約束をしてから遊びに行くことも大切です。
④ 急な天候の変化に注意!
キャンプやバーベキューなど山や川に遊びに行く機会も多くなるこの季節。
しかし夏は急な天候の変化も多く、最近は災害級のゲリラ豪雨なども各地でみられています。
大雨が降ると川の水の量が増えたり流れが急になったりします。
万が一に備えてライフジャケットを着用して遊び、天気が怪しくなってきたら早めに切り上げるようにしましょう。
また山で大雨が降ると水をたっぷり含んだ土砂が急に流れ出す土石流が起こる可能性があります。
土石流はとてつもないパワーとスピードで周囲の木や石などを巻き込みながら一気に流れていくので子どもだけではなく、大人も注意が必要です。
大雨が降ったときに岩がゴロゴロ鳴り出したり木がきしんだり、川の水位が増える・減る、水が濁ったり流木が混じり始めたら要注意!
川の流れから垂直の斜面に向かって逃げましょう。
子どもは静かに溺れる
映画などで人が溺れるシーンは手足をバシャバシャさせて「助けてくれ〜!」ともがくイメージがあると思いますが、実際に人が溺れるときは静かに溺れます。
溺れそうな人は呼吸をすることに精一杯になってしまい手足をバタつかせたり声を出す余裕がありません。
とくに子どもは「何が起きているかわからない」状況になってしまうため、身動きがとれずに静かに溺れます。
このように静かに溺れていく様子を本能的溺水反応と呼び、大人も子どもも同じ現象が起こることがわかっています。
とくに子どもは沈むスピードが早く、水中にいる時間が5分を超えると脳に後遺症が残るリスクも上がります。
また冷たい水より温かいお湯のほうが後遺症が残ったり死亡するリスクが30倍も高いことから日々のお風呂の時間にはとくに注意が必要です。
溺れてしまったらどうしたらいい?
どんなに注意をしていても事故が起こってしまうことがあります。
意識がある場合
① 一刻も早く水から引き上げる、近くに大人がいる場合は応援を呼ぶ
② 平な場所に寝かせる
③ 意識があるか確認する
④ 意識があれば子どもを安心させる
⑤ 水を吐いた場合には吐物を誤嚥しないよう体勢を整える
⑥ 病院を受診する
意識があって普段通りの様子であればしばらく様子を見てもよいですが、時間が経ってから体調が変化することもあるのでできれば受診するのがよいでしょう。
たくさんの水を飲んでしまうこと自体もリスクがありますし、どんな水を飲んでしまったかによっても危険性がかわります。
受診するときには溺れた場所やそのときの状況をしっかりと伝えるようにしましょう。
意識がない場合
① 一刻も早く水から引き上げる、近くに大人がいる場合は応援を呼ぶ
② 平な場所に寝かせる
③ 意識があるか確認する
④ 意識がなければ救急要請をする
⑤ 心臓マッサージを行う
水を飲んだかも?!とお腹を圧迫して水を吐かせたくなるかもしれませんが、誤嚥を起こす危険性もあるのでやめましょう。
心臓が止まっている時間が長くなればなるほど後遺症を残すリスクがあがるため、救急隊の指示に従い、心肺蘇生(心臓マッサージ)を続けます。
慣れない人工呼吸を挟んで心臓マッサージが中断されてしまうのであれば無理にやらずに、ひたすら心臓マッサージを続けましょう。
まとめ
夏ならではの水遊びや日本の文化のお風呂に浸かることなど、私たちの生活は水と密接しています。
その楽しさを子どもと共有するだけでなく、水のもつ怖さも一緒に学びながら生活していきたいですね。
子どもの不慮の事故は溺水だけではありません。
さまざまな事故を簡単にまとめているので、子どもや家族を守るために時間があるときに読んでみてくださいね。
過去にどんな危険や事故があったかを知るだけでも事故防止に繋がります。


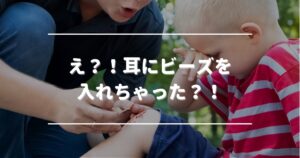

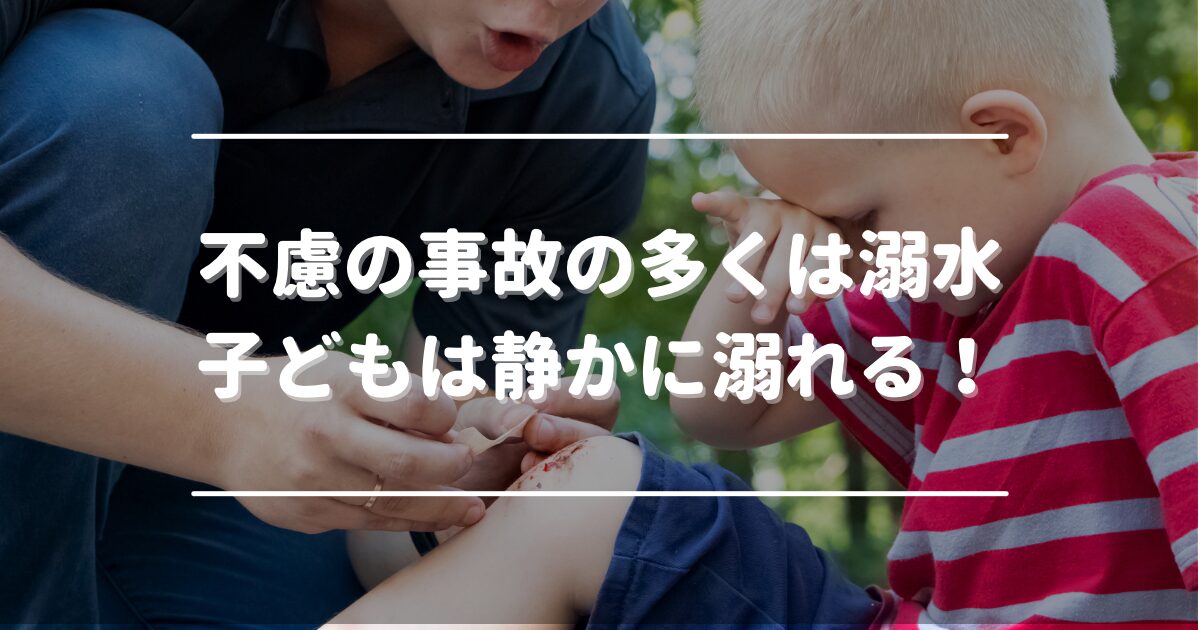

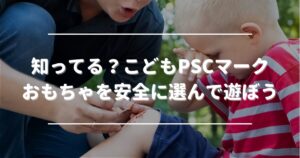




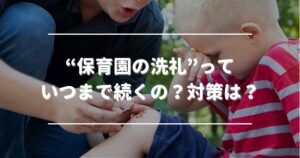
コメント