保育園ご入園おめでとうございます!
新生活にドキドキする気持ちや、決めたこととはいえ子どもを預けて働くことに寂しさや心配な気持ちなど、親子ともに緊張した毎日だと思います。
緊張から解放され、どっと疲れのでる週末…子どもも、パパもママも体調を崩してはいませんか?
保育園生活が始まったということは、巷でよく耳にする“保育園の洗礼”を受けるということ…。
洗礼とはどんなものでしょうか?何かできる対策はあるのでしょうか?
“保育園の洗礼”とは?
保育園の洗礼とは、保育園に通い始めた子どもが次々に風邪や感染症をもらって体調を崩し、短期間でお迎え(早退)の要請やお休みを繰り返すことです。
慣らし保育の間にお休みを繰り返すとなかなか子どもが保育園生活に慣れないですし、せっかく仕事復帰したのに早退やお休みばかりだと周りへも気をつかってしまいモヤモヤしますよね。
仕方ないこととはいえ、なんとか対策をしたいところ。
保育園の洗礼はいつまで続く?
入園直後の慣らし保育の頃から体調不良を繰り返し、多くは数か月が経った夏頃には落ち着いてくるでしょう。
しかし集団生活をしていると1年を通してさまざまな感染症が流行ってしまうので、最初の1年が終わるまでは頻繁な体調不良やお迎え要請が続くことを覚悟したほうがよさそうです。
洗礼を受けないこともある?!
保育園生活が始まってもあまり体調を崩さず「保育園の洗礼を受けなかった…?」ということもあるかもしれません。
体質による影響も大きいと思いますし、どんな違いがあるのか明確にはわかりませんが、お兄ちゃんやお姉ちゃんがいる子どもはわりと洗礼を受けにくい傾向があるような…。
きょうだいがいると上の子がかかった風邪がうつってしまい、入園前からいろいろな菌やウイルスに触れる機会が多いからかもしれません。
入園前から児童館や子育て支援センターなど地域の子どもたちが集まって遊ぶ場所へよくお出かけしていた子どもも洗礼を受けにくいことがありそうです。
入園前から少しずつ菌やウイルスに慣れておくのも対策の1つかもしれませんね。
どんな症状がでることが多い?
初めての集団生活のため今までかかったことのない菌やウイルスの風邪や感染症にかかります。
とくに感染力の強い病気が流行ると特定のクラスだけではなく、保育園全体で体調を崩す子どもが増えてしまいます。
春の間はとくに子どもの体調のこんなポイントに注目してみましょう。
発熱
発熱をきっかけに体調不良に気がつくことが多いです。
毎朝の登園前にも熱を測って行くと思いますが、保育園で発熱してお迎え要請がくることもしばしば。
とくに一気に体温が上がるときには熱性けいれんが起こりやすくなるので保育園からも急ぎでパパ、ママへ連絡を入れるようにしています。
保育園からの連絡には気がつけるようにしておきましょう。
なんとなく身体がポカポカしていたり、ぽけーっとする様子があるときも注意してみていきましょう。
咳、鼻水
最初のうちは常に咳や鼻水がでていて、もはやいつから体調を崩し気味でいつ治っているのか…と疑問に感じると思います。
咳や鼻水で息苦しそうにしていないか、食事や水分がとりにくくなっていないか、ぐっすり眠れているかなどを気にかけましょう。
子どもはお顔が小さいので鼻と耳を繋ぐ耳管が短く太く、傾きも水平に近いです。
そのため喉や鼻からの細菌やウイルスが耳に入りやすく、中耳炎も起こしやすいです。
咳、鼻水が続くときは中耳炎を起こしていないか(耳をよく触って気にしている、耳だれがあるなど)も気にかけてみましょう。
下痢
いつもよりお腹がゆるくなっていないか、うんちの形をよく見ましょう。
いつもより回数が多い、水っぽい、すっぱい臭いがするときは要注意です。
嘔吐
胃腸炎は感染力が強いのでクラスの誰かが吐いてしまうとあっという間に広がってしまいます。
クラスや保育園全体の流行状況も合わせて気にかけましょう。
家族がもらってしまい一家共倒れもあるあるなので、看病するパパ、ママも気をつけましょうね。
発疹
肌にぷつぷつがあるときも要注意です。
あせもや虫刺されのこともありますが、水痘(水ぼうそう)や麻疹(はしか)、伝染性膿痂疹(とびひ)など登園禁止になる感染症もあるので、全身をくまなくチェックして、気になるぷつぷつにすぐ気がつけるようにしましょう。
食欲がない
他の気になる症状がなく食欲がないだけならしばらく様子を見ても問題ないです。
しかし食事をあまりとらず機嫌が悪かったり、元気がない様子のときは体調が悪い可能性があります。
喉が腫れていたり、口の中に発疹ができているときは痛みや違和感から食事を嫌がることもあるので、発疹ができていないか口の中もチェックしてみましょう。
元気がない、ぼーっとしている
とくに何か気になる症状が出ていなくても、なんとなく元気がなかったり、ぼーっとする様子が多いときも体調不良の前兆のことも。
普段から子どもの様子をよーく見てるパパ、ママの「なんか変」は当たるものです。
よく寝る
慣れない新生活で落ち着かなかったり、興奮してしまって疲れているだけのこともありますが、いつもよりよく寝るときはその後の体調を気にかけましょう。
子どもは「だるい」などの身体の違和感を言葉で伝えられないので、よく寝ているときは体調不良の可能性があります。
また咳や鼻水などで夜間の睡眠がしっかりとれていないため日中も眠たいこともあるので、しっかり眠って身体を休めることができているかもチェックしましょう。
何かできる対策はある?
体調不良は親も子もしんどいので、できれば健康に過ごしたいもの。
何かできる対策はあるでしょうか?
手洗い・顔洗い・足洗い
帰ってきたら手洗いをするのは当たり前ですが、できたら顔も一緒に洗って、欲を言えばそのままお風呂に入ってしまうのがベストです。
子どもたちは保育園でいろいろなものを触り、口に入れ、お友だちの咳や鼻水の飛沫をノーガードで受けて生活しています。
保育園でもできる限りおもちゃや環境が清潔に保たれるように掃除していますが、全てを防ぐのは到底不可能で、誰と接触したかは追いきれません。
そのため全身に菌やウイルスをくっつけて帰ってきたと思って、その後の対策を考えましょう。
足を洗い、着ていたお洋服を着替えるだけでもだいぶ違うと思います。
子どもだけではなく、パパ、ママへの感染対策にもなりますよ。
よく寝て体力回復
身体が疲れていると体調を崩しやすくなります。
帰ってからやることが多くて大変ですが、お風呂、夜ごはんをなるべく早めに済ませて、早寝する習慣を心がけましょう。
パパ、ママも仕事と子育ての慣れない両立生活で疲れてしまうので、よく寝て体力回復に努めましょうね。
よく食べて抵抗力アップ
保育園に仕事に時間がないなかですが、できるだけバランスのとれた栄養満点な食事を意識しましょう。
ネットスーパーや作りおき、冷凍食品などを駆使して風邪に負けない身体を目指しましょうね!
野菜をよく食べる子どもほど風邪をひきにくく、ひいてしまっても悪化しにくかったという調査もあります。
カラフルな野菜でビタミンをとって、免疫力アップ!
鼻水をこまめに吸う
ちょっとした鼻水でも放っておくことで睡眠の質が落ちて体力が奪われたり、中耳炎など別の病気に繋がってしまったりします。
子どもが上手に鼻がかめるようになるのは2〜3歳頃なので、それまでは鼻吸い器でこまめに鼻水をとってあげましょう。
とくにお風呂あがりは身体が温まって鼻水が緩くなり吸いやすくなります。
泣いて嫌がってしまうと可哀想ですが、体調が悪化する前の対策として心を鬼にしてがんばりましょう。
早めの受診を心がける
小さな体調不良のきっかけを見つけたら、早めに受診するようにしましょう。
早めに薬などを貰えると悪化せずに乗りきれることも。
ただし発熱してすぐのタイミングで受診をしても時間をおいてから検査に出すものもあるため、連日受診する可能性があることを頭の片隅においておきましょう。
体調を崩す前に考えておきたいこと
どんなに対策していても体調を崩してしまうこともあるでしょう。
いざというときに慌てないように事前に考えておきたいことをまとめました。
かかりつけの病院を決めておく
普段から通っているかかりつけの病院があると、いざというときも相談・受診しやすいです。
今までかかった病気や処方された薬のことも全て把握してくれているため心強いですね。
小児科以外にも子どもを診てくれる皮膚科や耳鼻科もお世話になることが多いので調べておくとよいでしょう。
土日祝日も対応している病院を調べておく
かかりつけの病院を決めていても、子どもがいつ体調を崩してしまうかはわかりません。
そのためかかりつけ以外にも土日や祝日に対応している病院や、夜間に診てくれる病院などを調べておくと安心です。
大きな病院に紹介状を持たずに受診すると“選定療養費”という診療代とは別にかかるお金があったり、夜間には“時間外加算”として割り増しでかかるお金もあるため、受診する病院がどんなところなのかも調べておくと金銭面の目安も知ることができます。
病児・病後児保育を調べておく
もちろん子どもの体調がよくなるのが優先ですが、なかなかすっきり治らなかったり、登園許可がおりるまで時間がかかってすぐに仕事復帰できない…なんてことも起こるでしょう。
いつまでも仕事の休みをとり続けるわけにはいかないときに病児・病後児保育が使えると安心です。
しかし春先〜夏頃は同じように利用したい人が増える季節のため、なかなか空きが見つからないことも…。
病児・病後児保育がどこにあるか、当日の朝は何時まで申し込みができるか、キャンセル待ちはあるか…などを調べておくと万が一のときも慌てずに済みますよ。
家族の予定を共有しておく
とはいえ、どんなに対策していても体調を崩すことはあるし、お呼び出しがあったらお迎えに行かなくてはいけません。
パパ、ママでお互いの仕事の予定を共有しておくと“誰が迎えに行くか問題”が少し解決しやすくなりますよ。
仕事の内容によって「今日はどうしても外せない日」「比較的融通がきく日」などあると思います。
近所に手伝ってもらえるじーじ、ばーばが住んでいるときは協力をお願いすることも検討して、仕事と子育てのいいバランスを考えていきましょうね。
ゆっくり休もう!
パパ、ママは仕事と子育ての両立で大変ですが、パパ、ママから離れて集団生活を送る子どもも大変です。
お家ではできるだけゆっくり過ごし、みんなが回復時間をとれるように無理のない生活を送りましょう。
保育園や仕事を休んだ日には開き直ってのーんびりしましょう!
困ったときの連絡先
子どもの体調不良時はパパ、ママも不安になると思います。
困ったときに相談できる窓口を知っておくことで、何かあったときも冷静に対応できるでしょう。
#119
119番通報は誰もが知っている通り消防機関に繋がり救急車を要請できる番号。
41.5℃以上の高熱があるとき、けいれんしているとき、顔色や唇の色が悪く苦しそうなときなどは迷いなく救急車を要請しましょう。
救急車内では救急救命士が救急救命処置として治療をしながら病院まで付き添ってくれます。
#7119
救急車を呼ぶか判断に迷ったときは#7119の救急相談電話にかけて相談しましょう。
地域によって救急相談センターや救急安心センターなど名称は違いますが、#7119は消防に直結しています。
相談の結果、救急車を呼んだほうがいい状況であればその場で救急車の要請ができます。
逆に緊急性が高くないと判断された場合は受診のタイミングを聞くことができるので、迷ったときはアドバイスをもらいましょう。
#7119は全年齢が対象で、24時間365日利用できます。
#8000
#8000はこども医療電話相談事業の番号で、119や#7119より緊急性の低い相談窓口です。
対象は0歳〜15歳くらいまでの子ども専門の窓口で、看護師や小児科の医師に繋がる電話です。
多くの地域で19:00以降から朝まで、休日などに相談することができます。
夜間でも病院へ行ったほうがいいか迷ったときや頭をぶつけたあとに様子を見ていいかなどの判断をあおぐことができます。
適切な対処の仕方や受診の目安を聞くことはできますが、診断や治療はしてもらえないので必要に応じて病院を受診するようにしましょう。
地域によって相談できる時間が異なるので厚生労働省の子ども医療電話相談事業のページで確認しておきましょう。
まとめ
子どもはたくさんの菌やウイルスと戦いながら時間をかけて強くなっていきます。
何度も繰り返し菌やウイルスに出会うほど、身体がその菌やウイルスと戦って勝てるようになり、体調を崩しにくくもなります。
最初のうちは負けてしまうかもしれませんが、ゆっくり休んで回復していきましょう。
慣れない新生活ですが全国のパパ、ママ仲間と一緒に乗り越えていきましょうね!
おちゃ先生も働くパパ、ママ、新生活を楽しむ子どもたちを応援しています!
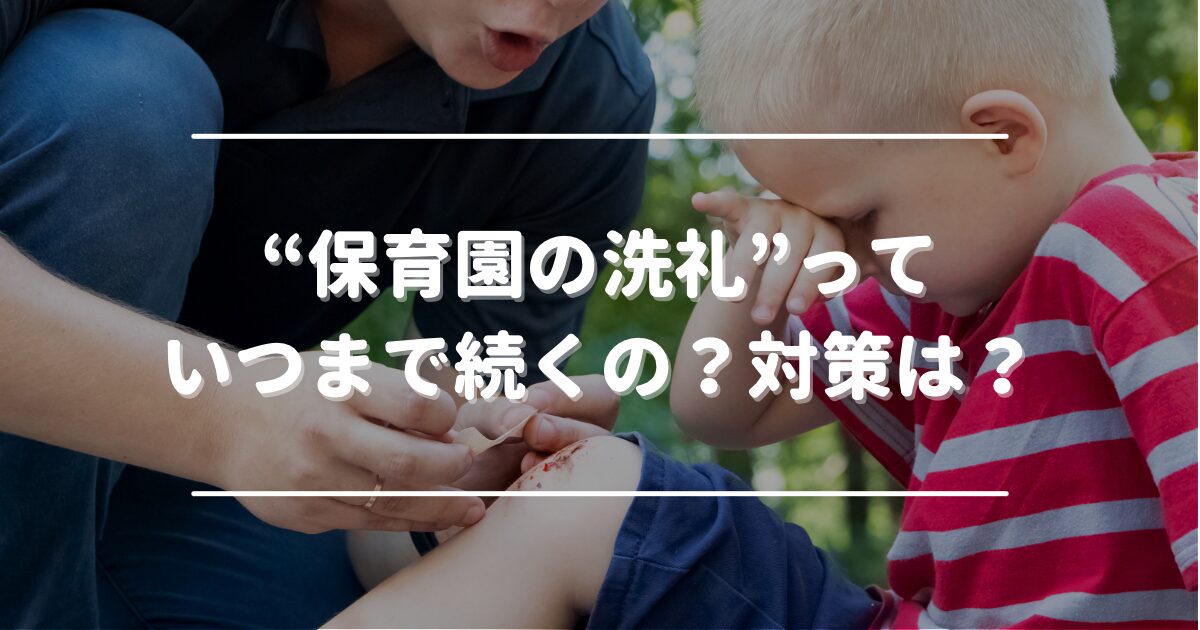

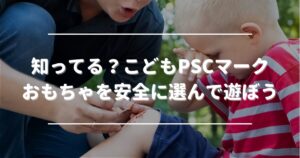


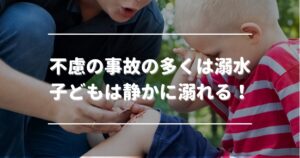



コメント