「ミルクで育てると赤ちゃんが太っちゃうのって本当ですか?」「赤ちゃんが太ったら可哀想なのでミルクはあげたくないです。」といったお話をよくいただきます。
“ミルク育児は赤ちゃんが太る”と聞いたことがある方も多いと思いますが、それって本当?
今回はミルク育児の赤ちゃんは太るの?どれくらい飲んだらいいの?という疑問を解決していきます。
赤ちゃんが太るってどういうこと?
私たち大人が“太る”のは、食べ過ぎや運動不足により摂ったエネルギーが消費されずに溜め込まれていくからです。
大人の肥満はこのような生活習慣の乱れによるもの。
では、赤ちゃんはどうでしょうか?
大人のようにエネルギーを溜め込んで体重が増えているわけではなく、赤ちゃんの体重の70〜80%は水分であるため、体重あたりの水分量が多い状態です。
どんどん動けるようになってくると筋肉などがついてきて、水分以外の割合も増えてくるため急激な体重の増加もなくなってきます。
また赤ちゃんの時期に脂肪細胞が増えることは健やかな成長に不可欠であり、正常なことです。
脂肪細胞には成長期の身体をつくり、ホルモンも分泌する大切な役割があります。
このような理由から、大人の体重が増えることと赤ちゃんの体重が増えること、つまり大人の肥満と赤ちゃんが太ることは大きな違いがあることをまずは知っておきましょう。
ミルクと母乳のカロリーの違いは?
ではなぜミルクのほうが太ると言われてしまうのでしょうか?
粉ミルクのカロリーはメーカーや商品ごとに差はありますが、大体100mlあたり約66〜68kcalです。
母乳は100mlあたり約66kcalのため、カロリーだけでいうとあまり大きな差がないことがわかります。
では次にタンパク質量を見てみましょう。
粉ミルクのタンパク質量は100mlあたり約2.2〜2.4gに対し、母乳は100mlあたり1.7gとやや少なめです。
タンパク質は消化に時間がかかるため、母乳育児の赤ちゃんに比べてミルク育児の赤ちゃんのほうがうんちの回数も少ない傾向があるともいわれています。
そのため“ミルクは腹もちがいい”などと言われていたりして、母乳のように好きなタイミングで好きなだけ飲む=自立哺乳をすると太りやすいと思われているのではないでしょうか?
実際、ミルクの間隔をあまりあけずに次のミルクをあげてしまうと赤ちゃんが満腹で苦しくて不機嫌になったり、吐き戻してしまったり、便秘になってしまうこともあります。
消化のために胃腸への負担もかかるため、ミルクのあげすぎには注意が必要です。
厚生労働省が発行している授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)にも“完全母乳栄養児と混合栄養児の間に肥満発症に差があるとされるエビデンス(=証拠、根拠)はない”と記載されているため、月齢に合わせた適切な量を与えることに間違いはありませんし、ミルク育児=太るわけではありません!
適切なミルクの量とは?
月齢に合わせた適切なミルクの量はどれくらいなのでしょうか?
1回あたりのミルクの量、時間の間隔、1日のミルクの回数を一覧にまとめてみました。
| 日齢/月齢 | 1回あたりの哺乳量の目安 | 間隔 | 1日の回数の目安 |
| 生後1日 | 20ml | 2〜3時間 | 8〜12回 |
| 生後2日 | 30ml | 2〜3時間 | 8〜12回 |
| 生後3日 | 40ml | 2〜3時間 | 8〜12回 |
| 生後4日 | 50ml | 2〜3時間 | 8〜12回 |
| 生後5日 | 60ml | 2〜3時間 | 8〜12回 |
| 生後6日 | 70ml | 2〜3時間 | 8〜12回 |
| 生後7日 | 80ml | 2〜3時間 | 8〜12回 |
| 〜1か月 | 80〜120ml | 3時間ごと | 7〜8回 |
| 1〜2か月 | 120ml〜140ml | 3〜4時間ごと | 6〜7回 |
| 2〜3か月 | 140ml〜160ml | 3〜4時間ごと | 6〜7回 |
| 3〜4か月 | 160ml〜200ml | 4時間ごと | 6〜7回 |
この一覧表はあくまで目安であり、調乳するときに“これくらいの量を用意すれば過不足ないですよ”という数字です。
実際は赤ちゃんの体重によって必要なミルクの量が変わってきたり、一度に飲みきれるときとあまり飲んでくれないときのムラがあったりと、目安の通りにはいかないことがほとんどです。
そのためミルクの量は1回量ではなく、1日に必要な量を飲めているか?で考えましょう。
赤ちゃんが1日に必要なミルクの量は計算式で出すことができます。
1日150ml/体重1kgあたり
が必要量とされています。
では問題です。
生後3か月の体重7200g(=7.2kg)の赤ちゃんが1日に飲むミルクの必要量は?
150ml×7.2kg=1080ml
ということで、答えは1080mlですね。
1日で1080ml飲めばいいということになるので、1回あたり130mlしか飲めなくても、200ml飲んでもOKということです。
夜間にまとまって眠れる赤ちゃんなら寝る前のミルクをたっぷりあげて、夜はミルクの間隔をあけて赤ちゃんもパパ、ママもゆっくり眠るなんて調整もできるようになりますね。
慣れるまでは計算しても「??」となってしまうかもしれませんが、1日のトータル量で考えられるようになると飲みムラに対する心配や不安が少し軽くなると思います。
ミルクの量が足りているサイン
とはいえ、目安量をあげていても赤ちゃんがミルクを飲んで満足しているのか?1回量が足りていたのか?は気になるところだと思うので、ミルクが足りているときのサインをまとめます。
体重が増えている
赤ちゃんは生後3〜4日頃に一時的に体重が減る“生理的体重減少”が起こります。
これは生まれたばかりの赤ちゃんはまだ上手に哺乳ができないため、飲む量より汗やおしっこ・うんちで失われる水分量が多いためとされていますが、生後1週間程度で出生体重に戻るので安心してくださいね。
その後は生後3か月頃まで1日あたり平均25〜30g程度ずつ体重が増えていきます。
生後3か月以降は15〜20g程度ずつ体重が増えていきます。
ベビースケールなど1〜5g単位など細かく測定ができる体重計があると、日々の体重の変化がよくわかります。
わざわざ購入しなくてもレンタルできたり、お住まいの地域の保健センターなどで測定できたりします。
赤ちゃんの体重を測るときは、着ている洋服によって重さに差が出てしまうためできる限り同じ格好で測りましょう。
おすすめはおむつ替え直後で、何も着ていない裸の状態です。
おしっこが出ている
赤ちゃんはまだ膀胱の機能が未熟なため、少量のおしっこを何度もします。
しっかりミルクが飲めている赤ちゃんであれば、1日に10回以上のおしっこが出ます。
身体の成長とともに膀胱も成長していくのでその回数は減っていきますよ。
血色がいい
しっかりミルクを飲めている赤ちゃんはほっぺに赤みがあり、肌に弾力や透明感があります。
唇がカサついていないかもわかりやすい指標になるので、日頃からよく観察してみましょう。
ごきげん
お腹が満たされていると赤ちゃんもごきげんに過ごせます。
ミルクの目安量に足りていなくても、日々体重が増えていて、赤ちゃんが元気でごきげんに過ごせていたらそこまで心配しなくても大丈夫です。
ミルクの量が足りていないサイン
一方で赤ちゃんにミルクが足りていないときにはこんな様子がみられることがあります。
体重が増えない
赤ちゃんの体重の増え方の目安は“体重が増えている”の項目で触れましたが、日々の体重の増えがあまりよくないときはミルクの量が足りているのか確認してみましょう。
しっかり飲めているように見えてもそもそも量が足りていないこともあれば、消化・吸収に問題があることもあります。
ミルクを飲んだ量と体重の増え方を記録してみて、長く続くようであれば原因を探る必要があるのでかかりつけのお医者さんなどに相談してみましょう。
おしっこが出ない
赤ちゃんは1日に何回もおしっこが出ますが、回数が少なかったり色が濃い、臭いが強いときには水分不足の可能性があります。
おしっこが1日に5回以下のときには要注意です。
便秘気味
赤ちゃんも便秘になることがあります。
母乳育児の赤ちゃんに比べてミルク育児の赤ちゃんは便秘になりやすい傾向がありますが、水分が足りないとよりうんちが出にくくなってしまうことがあります。
うんちの回数が少ない、お腹がぽんぽんに張ってしまう、うんちのときに強くいきむ、痛くて泣いてしまうなどがあれば便秘の可能性もあります。
かかりつけのお医者さんなどに相談してみてくださいね。
哺乳後にもミルクを欲しがる
ミルクを飲み終わった後も不機嫌でもっとミルクを欲しがったり、口をぱくぱくさせる様子があればミルクの1回量が足りていない可能性があります。
またミルクをあげてから1〜2時間で空腹で泣いてしまうときもミルクが足りていないことがあります。
そのようなときはいつもより少し多めにミルクをあげてみて、ごきげんでミルクの吐き戻しがなければミルクの量を増やしてあげるとよいでしょう。
まとめ
赤ちゃんの成長や発達、体調は個人差がとても大きいです。
そのため赤ちゃんの見た目や体重だけを見て自己判断でミルクの量を調整してしまうのは赤ちゃんの正常な発達を妨げることになるかもしれません。
ここまであげてきたものはあくまでも“目安”になるため、気になることがあったときにはかかりつけのお医者さんや地域の保健師さん、お住まいの地区にある子育て窓口などに相談してくださいね。
赤ちゃんが泣くのは空腹なだけではありません。
泣いたからミルクにしてしまうと体重が増えすぎる原因になってしまうので、おむつを替えたり、部屋の温度や洋服の枚数を確認したり、眠たくないかなど赤ちゃんが伝えたいことをキャッチしてみましょう。
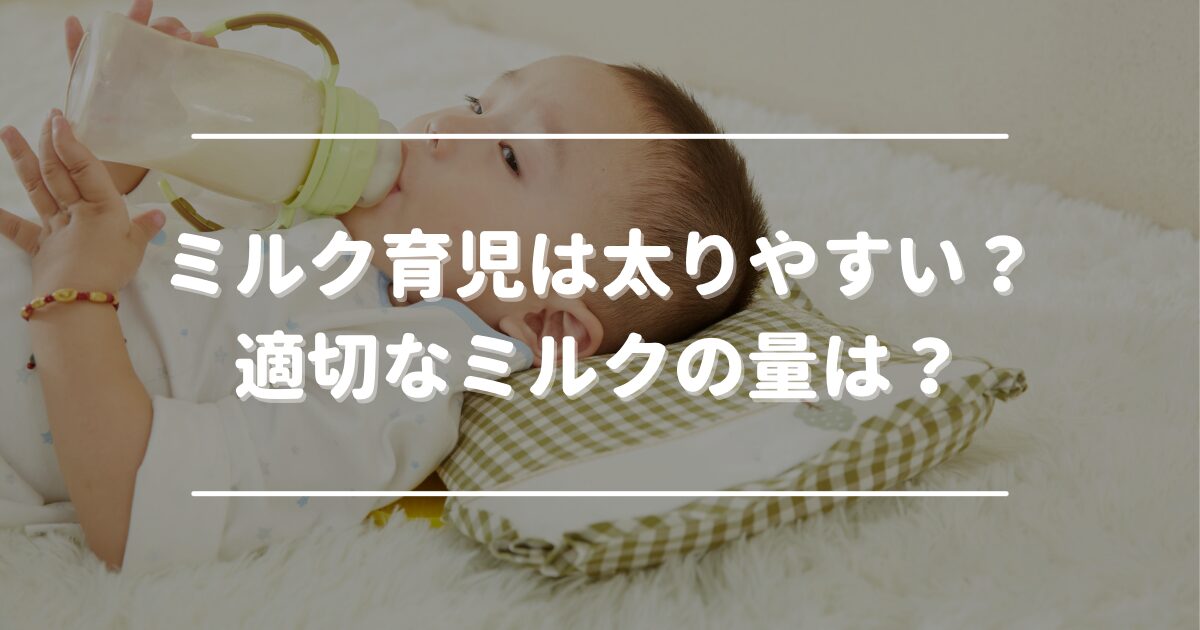
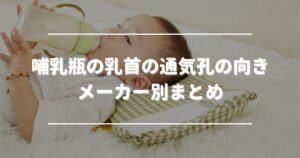
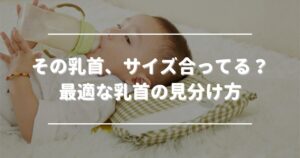
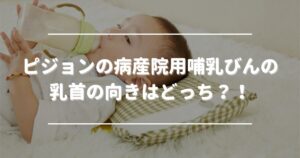
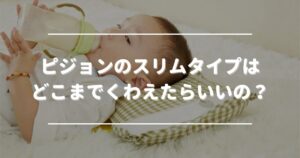
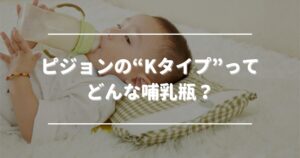
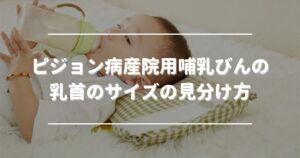
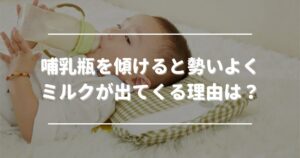
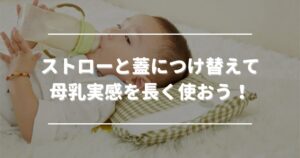
コメント