抱っこで寝かしつけ、このままベッドで眠ってくれたらやーっとパパ、ママの自由時間…と思ったのに〜!!
ベッドに背中がついた途端「ぎゃ〜〜〜!!」背中スイッチ発動!!
また抱っこで寝かしつけやり直しだ……ちょっと待って!そのお目覚めスイッチ、実は背中ではなくて別の場所についているかも?!
寝かしつけに悩むパパ、ママ必見!上手にベッドで眠ってもらうコツを紹介します!
背中スイッチはお腹スイッチ?!
“背中スイッチ”とは赤ちゃんを抱っこで寝かしつけた後、布団に下ろすとまるで背中にあるスイッチを押されたかのように急に目を覚ましたり、泣き出したりする現象のことをいう育児界の俗語です。
抱っこで寝ついた赤ちゃんをベッドに下ろして泣いてしまうので背中にスイッチがあると思われがちですが、眠った赤ちゃんは背中がベッドに触れる前から覚醒を始めています。
見た目ではまだ眠っていますが、抱っこしている人から身体が離れるときに心拍が速くなることがわかっています。
つまり赤ちゃんは背中がベッドにつく背中スイッチで起きてしまうのではなく、抱っこしてくれているパパ、ママから身体が離れてしまう“お腹スイッチ”で目が覚めてしまうということになります。
ベッドに戻ると起きてしまう原因
抱っこで眠ってくれるとかわいいですが、ずっとそのままでは腕や肩が凝ってしまうし、寝ている間に済ませたい家事やパパ、ママののんびりタイムもとれません。
それに赤ちゃん自身も抱っこだと眠りが浅くなってしまってぐっすり眠れないという課題もあります。
なぜ目が覚めてしまうのか原因をみてみましょう。
赤ちゃんの姿勢の変化
赤ちゃんはまんまるなCカーブの姿勢を好み、安心して過ごせます。
ママのお腹の中にいた頃のように丸まった姿勢を想像してみてください。Cカーブの姿勢は身体全体を丸め、首からおしりまでの背骨がアルファベットのCの字のようになっている姿勢です。
抱っこのときはこのCカーブの姿勢で安心して眠っているのに、ベッドに戻ると平らな布団に仰向けに寝かされて身体全体が真っ直ぐ伸びてしまうため赤ちゃんはびっくりしてしまいます。
この姿勢の変化が赤ちゃんの目が覚めてしまう原因の1つといわれています。
抱っことベッドの温度差
抱っこはパパ、ママの体温で温かいですが、戻ったベッドは冷たくひんやり。
この温度の変化も赤ちゃんの眠りを浅くする原因になります。
お部屋や布団を温めておいてあげるとぐっすり眠れるかもしれません。
自分のモロー反射でびっくり
眠っている赤ちゃんは周りの些細な音や自分のしゃっくりなどの刺激によってモロー反射が起こり、目が覚めてしまいます。
モロー反射とは赤ちゃんの原始反射の1つで、周りからの刺激に反応して手足をビクッと動かし両手を広げる動きです。
両手を広げたあとに何かにしがみつくような動きをするのは近くのものに掴まって危険を回避するためともいわれていて、生後4か月頃には自然に消えていく原始反射です。
モロー反射は脳の発達を促すためにも必要な反射なので抑えすぎてはいけないですが、しっかりとした睡眠をとるために一時的に落ち着かせてあげる必要はあります。
おくるみやスワドルを活用していきましょう。
上手にベッドに寝かせるコツ
せっかく抱っこで眠った赤ちゃんを、そのままベッドでぐっすり寝かせてあげたいですね。
上手にベッドに寝かせるコツを紹介します。
眠りが深くなってからベッドに寝かせよう
パパ、ママの抱っこからベッドに戻ってぐっすり眠れる赤ちゃんと、すぐに起きてしまう赤ちゃんがいます。
ぐっすり眠り続けている赤ちゃんの特徴として、抱っこしているパパ、ママの身体から赤ちゃんが完全に離れた瞬間に一気に眠りが深くなることが明らかになっています。
抱っこで寝かしつける時間も重要な要素。
抱っこで平均8分間眠ってからベッドに戻ると、そのまま寝続けられることが多いとされています。
その理由として赤ちゃんの寝始めの浅い睡眠から深い睡眠になるまで8分ほどかかるから。
ぐっすり眠ったタイミングでベッドに寝かせてあげると、そのままベッドでも眠れるかもしれません。
布団でくるんだまま寝かせよう
薄手のタオルケットやガーゼケット、寝かしつけ用の薄手のクッションなど、赤ちゃんのおやすみグッズでくるんだ状態で抱っこの寝かしつけをします。
ベッドに寝かせるときもあかちゃんをくるんだ状態のままにしてあげましょう。
これでベッドのひやっと感が軽減でき、モロー反射により手足のバタつきも優しく抑えられるでしょう。
ギリギリまでおなかをくっつけよう
冒頭で抱っこしているパパ、ママと身体が離れるときに眠りが浅くなるとお伝えしましたね。
ベッドにおろすときも腕を伸ばして寝かせるのではなく、抱っこしている姿勢のままパパ、ママの身体ごと一緒にベッドに近づきましょう。
できるだけゆっくり赤ちゃんの姿勢を変化させていくことが上手くいくコツです。
頭かおしりから着地しよう
背中が1番にベッドにつくと、抱っこの柔らかな感覚から急にベッドの平らなところに変化したことが赤ちゃんにすぐに伝わってしまいます。
頭やおしりを先に着地させ、少しずつベッドに触れる面積を広げていく感覚です。
途中で起きてしまいそうな気配を感じてもすぐに抱き上げずに、そのままの姿勢をキープします。(キツい姿勢のときもありますが、ちょっとだけ耐えて…!)
じわじわと腕を抜いていきましょう。
お腹にじんわりと重みをかけよう
無事に着地したあと、すぐに離れてしまうと赤ちゃんが変化に気づいて起きてしまうかもしれません。
赤ちゃんを完全にベッドに戻せたあとは、お腹全体にパパ、ママの腕をずっしりのせて、苦しくない程度にじんわりと重みをかけてみましょう。
まだパパ、ママとおなかがくっついていますよ〜!という感覚です。
その腕も少〜しずつ離していくと赤ちゃんは安心してぐっすり眠れるでしょう。
睡眠のリズムに合わせよう
赤ちゃんは月齢や成長に合わせて起きている時間と眠っている時間が変化していきます。
眠さのピークを超えてしまうと、むしろ不機嫌が強くなってしまい眠りにくくもなります。
赤ちゃんに「眠いなら寝ればいいのに」は通用しないので、眠くなるタイミングで寝かしつけてあげられるよう日々の様子をよく観察して生活リズムをつかんでいきましょう。
赤ちゃんの足をくっつけよう
ママのお腹の中では狭いから身体のあちこちがママと触れ合っている状態です。
眠るときも足がぶらぶら自由になっていると不安になってしまうので、赤ちゃんの足の裏同士をくっつけてあげたり、丸めたタオルなどを足の裏にくっつけて安心させてあげましょう。
お腹にじんわり重みをかけているときに、反対の空いているほうの手で赤ちゃんの足の裏をくっつけてあげる合わせ技もいいですね。
日頃からにぎやかな環境に慣れよう
ベッドで眠ってからも、ほんの少しの物音で起きてしまうとここまでの努力も水の泡…。
そうならないためにも普段から少しばかりにぎやかな環境で生活することに慣れてもらいましょう。
ぐっすりと眠れるように無音な環境をつくってしまいがちですが、静かな環境に慣れた赤ちゃんはフローリングが軋む音や食器の当たる音などでも目を覚ましてしまいます。
ザーっというママのお腹の中で聞いていた音に近いホワイトノイズや雨の音、波の音などを小さく流しておくと安心すると同時にちょっとの物音は気にせずに眠ることができます。
まとめ
どんなに頑張って寝かしつけても泣いて起きてしまう赤ちゃんはいると思います。
おちゃ先生も今だに寝かしつけには苦労するときはあるし、どんなに頑張っても抱っこを好む赤ちゃんはいます。
そんなときは潔く諦めてもいいですし、パパ、ママも一緒に泣いてしまってもいいんです。
ずっと泣いていても赤ちゃんが死んでしまうようなことはないですからね、いつかは泣き疲れて眠ります。
少しずつ赤ちゃんは眠り方を、パパ、ママは寝かしつけ方を身につけていきましょうね。
「うちはこんな寝かしつけ方が効いたよ!」という方法があるパパ、ママはぜひコメントで教えてください!
(コメントはおちゃ先生が確認してから公開されるので安心してください!掲載されたくない場合はそちらも含めてコメントくださいね!)
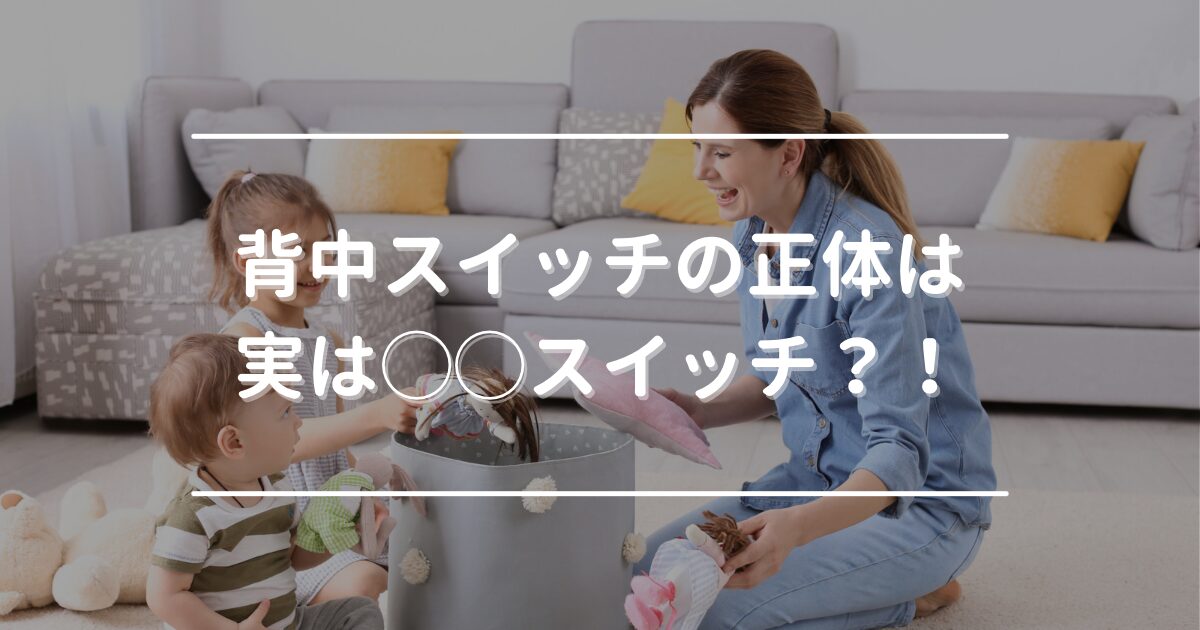








コメント