赤ちゃんの栄養源は母乳かミルクであることがほとんどです。
生まれてすぐの頃は飲む側も飲ませる側も上手くいかずに苦戦していたのに、気がつけばいつの間にかお互い上手になっていて、赤ちゃんもぷくぷく大きくなってきたかと思います。
赤ちゃんの口は、母乳やミルクを飲むために大人とは少し違うつくりをしています。
今しか見ることのできないかわいい口を、じっくり観察してみましょう。
吸啜反射ってなに?
赤ちゃんは口に入ってきたものをなんでもちゅっちゅと吸う原始反射があり、吸啜反射といいます。
妊娠20週頃から吸啜のような動きが見られ始め、ママのお腹の中にいるときからちゅっちゅと吸って、ごっくんと嚥下する一連の動きを練習してから生まれてきます。
そのため生まれて間もない頃から赤ちゃんは母乳やミルクを吸って飲むことができるのです。
この吸啜反射は離乳食を開始し始める生後6か月頃から1歳頃までには消失してしまうものなので、赤ちゃんのうちにしかみられないものです。
よく洗った指を赤ちゃんに吸ってもらうと、思った以上の強い力で吸われる感覚が感じられると思うので、ぜひ清潔にした指で試してみてその生命力に驚いてみてくださいね。
赤ちゃんの口の特徴
吸啜以外にも、赤ちゃんの口にはさまざまな特徴があります。
どんなものがあるでしょう?
おっぱいを吸いやすくする溝
赤ちゃんの口の中は母乳やミルクを飲みやすくするために特徴的な形をしています。
「おぎゃー!」と泣いて大きく開けた口の中をよく見てみてください。
上顎がアーチ状にぽっかり高くなっていませんか?
この上顎の天井のことを専門的には“口蓋”と呼びます。
そして赤ちゃんの口蓋にあるぽっかりとあいた溝のことを“哺乳窩”といいます。
“吸啜窩”なんて言われることもあります。
この哺乳窩は母乳やミルクの通り道のようなもので、ママの乳首や哺乳瓶の乳首をすっぽり収めることができます。
上顎と下顎のすきま
赤ちゃんは生まれてすぐの頃には歯が生えていませんが、にっこり笑ったときに前歯が生えてくる歯茎の位置にすきまがあって、しっかり口が閉じていないんじゃないか?と心配されることがあるかもしれません。
でもこれも母乳やミルクを吸いやすくするためのつくりのひとつ。
この上下の顎の間にあるすきまを“顎間空間”といいますが、赤ちゃんが哺乳中にうっかり口を閉じてしまってもママの乳首を潰さないようにあるすきまです。
ほっぺの内側のお肉
赤ちゃんのほっぺの内側の粘膜の下にある脂肪のふくらみを“ビシャの脂肪床”といいます。
このビシャの脂肪床は口の内側の面積を狭めて吸啜の圧をつくりだすためにあるといわれていて、哺乳窩でしっかり乳首を捉えてビシャの脂肪床で左右からしっかり支えて固定します。
早産児や低出生体重児はこのビシャの脂肪床が薄いこともあり、吸啜の弱さなどの哺乳の困難さが課題になることもあります。
そうでなくてもウトウトしてしまうなどで一時的に吸啜が弱くなってしまう赤ちゃんもいるので、ムセたり飲みこぼしたりしなければ、哺乳中に両方のほっぺを軽く抑えて圧迫してあげると飲みやすくなりますよ。
離乳食など母乳やミルク以外のものを食べるようになって口を動かす機会が増えるにつれて、このビシャの脂肪床も消失していきます。
しかし柔らかいものを食べ続けて噛む経験が少なかったり、なんでも丸飲みしてしまっているとビシャの脂肪床の消失が遅れるともいわれています。
そのため月齢や子どもの食べ方に合わせてしっかり噛めるメニューに変えていったり、もぐもぐする練習をしていきましょう。
仕上げ磨きのときにほっぺの内側を観察してみて、5歳を過ぎてもふくらみが気になるようであればかかりつけの歯医者さんへ相談してみてください。
まとめ
赤ちゃんって、人間って、とても神秘的!
お口にこんな特徴があったなんて驚きです。
今だからこそ楽しめる子どもの成長を噛みしめながらじっくり子育てを楽しんでくださいね。
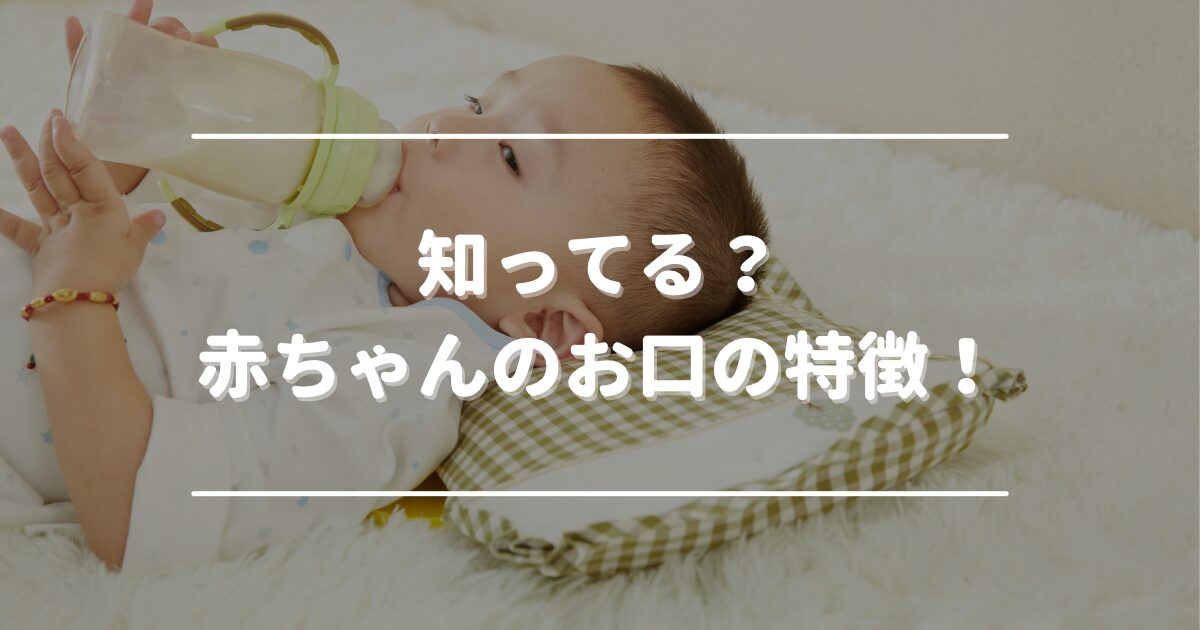
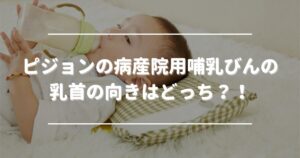
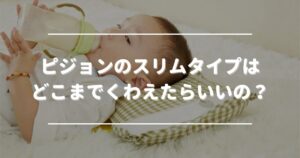
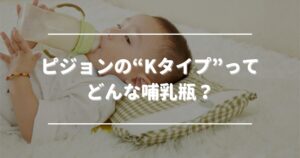
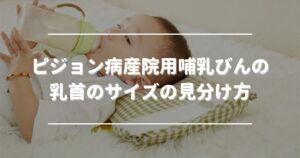
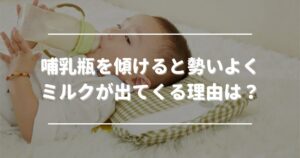
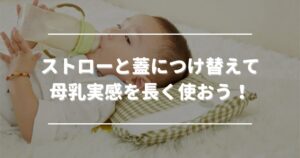
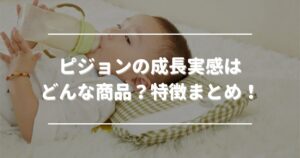
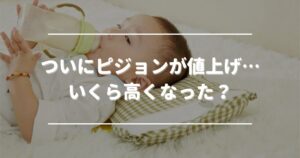
コメント