子どもは何歳頃からひらがなに興味をもち始め、読めるようになるのでしょうか?
いつからひらがなを教えようか悩んだり、他の子どもの様子と見比べて焦ってしまう気持ちもあるかもしれません。
今回は子どもがいつ頃から、どのようにひらがなの読み方をを学んでいくのか、楽しくひらがなに触れる遊びも一緒にご紹介します!
ひらがなに興味をもつのは何歳?
子どもがひらがなに興味をもち始めるのは4歳頃だといわれています。
読んでもらった絵本や身近なもののパッケージなどに書かれている文字に注目することがきっかけとして多いですが、個人差がとても大きいです。
2〜3歳頃からひらがなを認識し始める子どももいれば、小学校入学頃まであまり興味を示さない子どももいます。
子どもの興味関心が他に向いているタイミングで無理にひらがなを教えようとしてしまうと、“イヤな記憶”としてむしろ苦手意識が強くなってしまい、今後の学習に取り組みにくくなってしまうこともあります。
絵本やひらがなを扱ったおもちゃなどを用意しておき、子ども自身が手にとって遊び始めるまでそっと見守りましょう。
どうやってひらがなが読めるようになるの?
書くより先に読めるようになる必要がありますが、子どもはどのようにしてひらがなを覚えていくのでしょうか?
音韻認識ができるようになる
ひらがなが読めるようになる前に必要な力が音韻認識です。
音韻認識とは1つの単語、たとえば「みかん」が「み」と「か」と「ん」という3つの音でなりたっていると認識できる力ですが、子どもはほぼ無意識のうちに身につけています。
日本語は一音一文字(=1文字に1つの読みがある)でできているので、「みかんのみ」「みかんのか」「みかんのん」と文字が3つ当てられると認識できることがひらがなを読めるようになる第一歩になります。
ひらがなに興味をもつ
2〜3歳頃になると身の回りのありとあらゆるものを「これなに?」「あれなに?」と聞いてくる、なになに期がきます。
「絵本に書いてある、これはなんだろう?」と子どもが気づくことこそがひらがなへの興味の始まりです。
絵とは違う文字への疑問に丁寧に答えてあげることで、子どもが「これは読むものなんだ!」と気がつき、もっと知りたいと思うようになります。
ここでのポイントはひらがなを指さししながら読んであげることです!
指さしされた“あ”に注目して、その文字が“あ”だと認識できるからです。
名前や身近なものから始める
ひらがなは読むものだと理解した子どもは、もっともっと読んでみたい!となります。
なので家の中にひらがながたくさん散りばめて、読みたい環境をつくっていきます。
たとえばお皿やコップ、歯ブラシなどの身近なものに子どもの名前を書いてあげると「何か書いてある…?」「は、る、ひ…ぼくの名前だ!」と自分の名前のひらがなを覚えることができます。
さらに違うものを見たときに「“ひこうき”…あ!ぼくの名前と同じ“ひ”が入っている!」と次に広がり、“ひ、こ、う、き”と新しく覚えることができます。
おもちゃを片づける棚やバケツなどに“つみき”“えほん”などと書いて貼ってあげると、自然にひらがなに触れることができますね。
最初は拾い読みでOK!
拾い読みは文字を1つずつ追って読んでいく読み方で「も、も、た、ろ、う、は…ももたろうは!」と最後まで読み終えて初めて言葉を認識します。
ひらがなを覚えたてのときはロボットが読んでいるような、棒読みのような読み方になりますが、スラスラ読みができるようになるのは読む練習を重ねる必要があり、結構ハードルが高いもの。
まずは読めた楽しさ、新しいことができるようになった嬉しさを大切にしていきましょう。
ひらがなが好きになる!おすすめの遊び8選!
楽しく遊びながら自然にひらがなに触れられるおすすめの遊びをご紹介します。
① 音に合わせてパチパチ拍手
「み・か・ん♪」「お・む・ら・い・す♪」など音に合わせてパパ、ママがパチパチ拍手して、そのあとに子どもに真似してもらいます。
音遊びをすることで自然と子どもの音韻意識を育むことができ、言葉が音の集まりであることを意識できます。
慣れてきたら子どもに先導してもらい、パパ、ママがあとに続きましょう。
② “あ”から始まる言葉はな〜んだ?
「あめ」「あひる」「あいす」などなど…順番に言い合って遊ぶゲームです。
なかなか子ども1人で言葉が思い浮かばないときは「りんごは何色だっけ?」などとヒントをあげると、「あか!あ、だね!」と気がつくことができます。
たくさん言葉がみつかる音もあれば“ぬ”や“る”など大人でも難しい音もあるはずです。
新しい単語との出会いにもなるため子どもとわいわい楽しみましょう。
バスや電車などの移動時間や病院の待ち時間などもモノを使わずに楽しく静かに過ごせる遊びですよ。
③ しりとり
“あ”から始まる言葉はな〜んだ?で始まりの音が意識できるようになったら、次はしりとりで終わりの音にも注目できるようになりましょう。
言葉を構成する音の並び順を意識的に認識する能力も音韻認識の1つの力。
楽しみながら音の構造を学びましょう。
④ グリコ
誰もが子どもの頃にやったことのある遊び、グリコ。
じゃんけんをしてグーで勝てば「グリコ(3歩)」、チョキで勝てば「チヨコレイト(6歩)」、パーで勝てば「パイナツプル(6歩)」と音の数だけ先に進めて、ゴールを目指す遊びですね。
地域によってさまざまなローカルルールがあると思いますが、どれも音と同じ数だけ前に進めるということ。
ひらがなの学習、というと椅子に座って勉強しなくてはいけないイメージがありますが、身体を動かしながら身につけるのも大切な学びになりますよ。
⑤ 回文遊び
回文とは上から読んでも下から読んでも同じ言葉、たとえば「とまと」「きつつき」「しんぶんし」などのことです。
言葉を構成する音の並び順を入れ替えて新しい言葉を作る能力も音韻認識を育む大切な力のため、この言葉はどうかな?と確認するだけの遊びも学習になります。
回文にならなくても、「い、か→か、い」「い、る、か→か、る、い」など違う意味になる言葉との出会いも楽しめますよ。
⑥ 新聞紙からひらがな探しゲーム
新聞紙や広告を広げて共通のお題の言葉を先に見つけた人が勝ちというゲームです。
お題は自分の名前や好きな食べ物などなんでもOKで、見つけた文字にペンで印をつけておくとあとから振り返りもできていいですよ。
別の紙に“ぶどう”などお題を書いておいてあげることで「今なんの文字を探してるんだっけ?」を防いだり、まだ覚えきれていないひらがなでも見本と見比べながら探すことができます。
手先が器用な子どもははさみやのりを使って、見つけた文字を切り貼りして並び替え、ダイイングメッセージのような言葉や文章を作る遊びも集中して取り組めます。
これはひらがなだけではなく、カタカナや漢字を学習している小学生以上の子どもでも楽しく遊べるため、お兄ちゃんやお姉ちゃんなどとも一緒に遊ぶことができますよ。
⑦ 幼稚園・保育園の先生ごっこ
子どもは大人の真似が大好き。周りの大人のことをよく見ています。
お気に入りのぬいぐるみやパパ、ママが園児役になって、こども先生に絵本を読んでもらいましょう。
“ころころ”や“きらきら”といった擬音語が多い赤ちゃん絵本は文章も短く子どもでも読みやすいです。
赤ちゃん絵本はもう読まないかな?と思っているパパ、ママも、もう少し捨てずにとっておいて!
⑧ 知育絵本
いつもの絵本と同じように、そっとあいうえおの本も一緖に用意しましょう。
普段の読み聞かせのなかで自然と50音に触れることができます。
子どもに人気の絵本をまとめた記事もあるので、絵本選びに悩んでいる方はこちらも合わせて読んでみてくださいね!
まとめ
言葉の習得には個人差が大きいので、周りの子どもや月齢・年齢の目安と比べて焦ってしまうかもしれません。
でも学ぶ主体である子どもの気持ちをまずは大切にして、子どものペースで進めてあげてくださいね。
パパ、ママがにこにこして楽しそうにしている姿を見て、子どもも安心できます。
「学習!」と迫らずに楽しくのんびり遊ぶ時間をたっぷりとってみましょう。
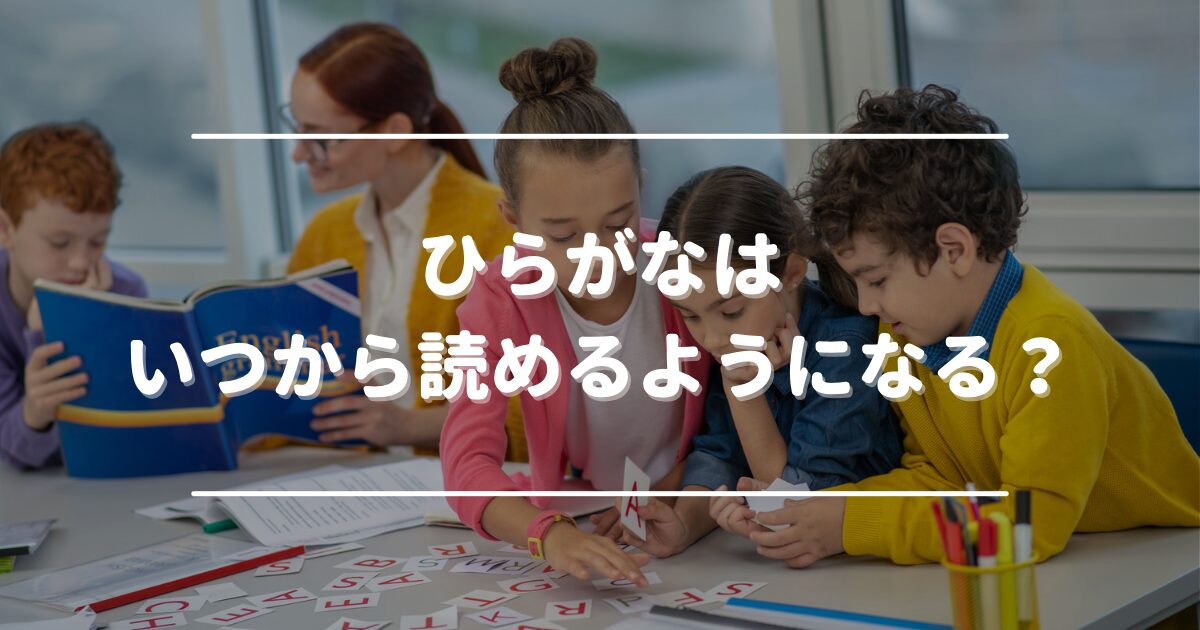
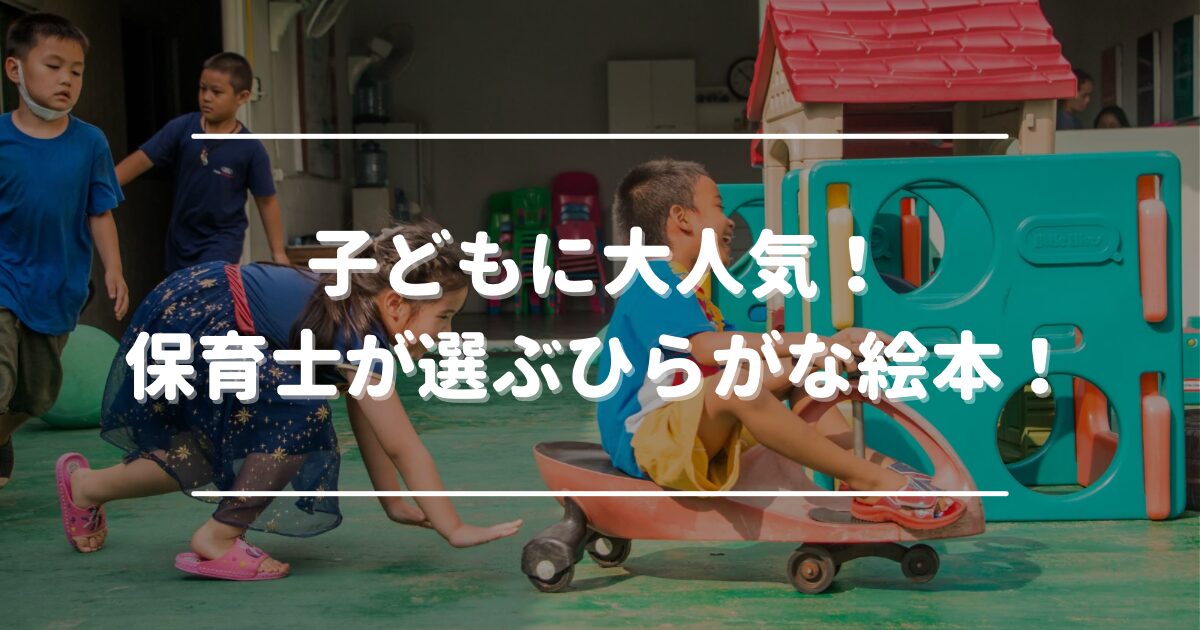
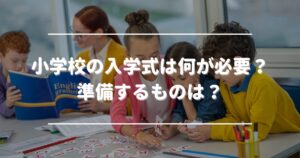
コメント