子どもは遊ぶのが仕事といわれるくらい、生活の中心に遊びがあります。
遊んで楽しい時間を過ごしているだけでなく、遊びのなかからさまざまな学びを得ています。
子どもは遊びから何を身につけているのでしょうか?
今回は遊びの重要性をみていきましょう。
子どもの遊びと大人の遊びの違い
子どもも遊びますが、もちろん大人も遊びます。
しかしその遊びがもつ意味には大きな違いがあります。
子どもがする遊び
子どもの遊びは日常的なものであり、自発的です。
自分で何かに取り組む、「やってみたい」という子ども自身の動機がきっかけで始まるものが遊びであり、そこで得た知識や経験、感性は蓄積されていきます。
年齢によってどんな遊びを好むのか、1人で遊ぶのか、誰かと一緒に遊ぶのかは違ってきますが、全ての遊びは子どもたち自身で行うもののことをさします。
大人がする遊び
一方で大人がする遊びの多くは“娯楽”であり、わざわざ時間をつくる必要がある非日常的なものです。
たとえばゲームやYouTube、映画鑑賞は日常生活のスキマ時間に行う受動的なものです。
娯楽で得たものは蓄積されず、消費されていきます。
“あそび”には物と物の間の隙間、ゆとりという意味もあります。
生きていくうえには“心のゆとり”=“心のあそび”が必要になるので、子どもにとっても大人にとっても遊ぶことはとても重要といえるでしょう。
子どもが遊びから身につける力
子どもが遊びを通して身につける力は“非認知能力”というテストの点数などの数字では測定できない力です。
非認知能力は大人になってから身につけるのはとても大変で、乳幼児期に1番身につくといわれています。
遊びでどんな力を身につけるのでしょうか?
やってみたい気持ち “自発力” “主体性”
子どもの遊びは自発的で、子ども自身の「やってみたい」気持ちから始まり、それがどんどん発展して継続していきます。
遊んだときの「楽しい」「面白い」という感情が「もっとやりたい」につながり、物や周囲の人にも主体的に関わることができます。
関わりが深くなるともっと楽しくなり、さらに興味関心を広げていくことになります。
生きるうえの原動力ともいえる自ら取り組む力が身につきます。
ここで大切にしたいのは、大人があまり口出しをせずに子どもが主体的に遊べるようサポートすること。
安全に遊べる環境を整え、見守る姿勢が大切です。
自分の体を知る “運動能力” “体力”
子どもは遊びながら自分の身体について学んでいきます。
歩く、走る、ジャンプする、登る、降りる、蹴る、投げる、転がる、回る、ぶら下がる、這う…などなど、自分の身体の動かし方を覚えてきます。
最初は上手くできなくても「やってみたい」の自発力があれば何度だって繰り返すことができ、ぎこちなかった動きもだんだんスムーズになっていきます。
どのくらいの力が最適かといった力加減も身につきます。
同時に心肺機能も向上するので、体力もついていきます。
自分で決める、自分で選ぶ “判断力”
パパ、ママは今までたくさんの経験をしてきたので「これがいい」「それはやめたほうがいい」という判断が適切にできますが、子どもにはまだその経験が多くありません。
でもその正しさは言葉で伝えるのが難しく、実際にやってみないとわからないものです。
子ども自身が自主的に判断する、自由に選ぶ経験を積み重ねていくことで適切な判断を学んでいくことができます。
身の危険や犯罪、周囲への許されない迷惑などどうしても止める必要があるときは別ですが、それ以外のことはまずは子どもが思うようにやってみるのが大切で、やる前から止めたり批判するのはやめましょうね。
その後に予想通りの「あちゃー」な出来事が起きても、一緒にどうしたらよかったのか考えれば次の判断に活かされます。
どうしたらいいか考える “思考力”
思考力は考える力、考え抜く力のことです。
子どもは遊びのなかで「どうやったらいいんだろう?」「こうしたらどうなるかな?」と何かを発見しようとしたり、考えながらチャレンジしています。
こうした経験を積み重ねることで、初めて出会う困難でも「どうしたら解決できるかな?」と考えていくことができます。
一方で子どもが考えたことに対して批判して責めたり、指示や命令をしてしまうと子どもは考えることをやめてしまいます。
子どもの考えを尊重する姿勢が大切です。
これは安全? “危機回避能力”
子どもはよく転びますが、赤ちゃんの頃から何度も転んでは立ち上がることを繰り返して、転ばずに歩く方法を身につけます。
それと同じように遊びのなかでさまざまな挑戦や失敗を繰り返して安全かどうか、危険はないかを判断できるようになります。
「こんな高いところから飛び降りても安全かな?」という疑問は、自分の運動能力を知っておく必要があるし、上手く着地できなかったらどうなるか?を想像しなくてはいけないし、どうやったら安全に降りることができるかを考えなくてはいけません。
最近の子どもは自分の身体を操作する能力が低下しているといわれています。
怪我を防止するためにも身体を動かす遊びを積極的に取り入れる必要がありますね。
見えないものをイメージする “想像力” ”感じる力“
想像力とは目の前にある物を別の物に見立てたり、今そこにないものを思い浮かべたり、自分が経験したことがないことや実際に見たり聞いたりしていないものについて考え、その感覚や概念を作り出す力のことをいいます。
「絵本の主人公はどんな気持ちかな?」「悲しそうな顔をしているけど何かあったのかな?」と察する力につながります。
子どもの想像力はとても自由で、ときに大人を驚かせるような型にはまらないものも。
ここで正しい知識や物の見方を教えたり正解を見つけさせる必要はありません。
むしろ子どもと一緒にそのイマジネーションの世界を楽しんで想像力を育む関わりが大切になります。
何かを創り出す “創造力”
創造力は英語でcreativity(クリエイティビティ)、想像したアイディアを実際の形にすることをいいます。
同じ読みの想像力と互いに深く関わり合っている力ともいえます。
何もないところから何かを生み出すためには、何を使うか、どうやって形にするかにじっくり向き合わなくてはいけません。
創造力は天才的なひらめきの力ではなく、何度も挑戦した経験の積み重ねが大切です。
失敗を責めることなく、前向きに取り組み続けられるような声かけや環境作りをしてあげたいですね。
ひたすら取り組める “集中力”
集中力は子どもが1つのことに注意を集めて取り組むことができる力です。
集中力が育つことは短時間で物事の成果を出すことにつながります。
子どもが黙々と何かに取り組んでいるときは声をかけずにそっと見守り、ときに「集中できているね、最後までできそうだね。」と応援することで集中力を切らさずに最後までやり遂げることができます。
人と関わる “社会性”
社会性はその名の通り社会の中で人と関わりながら過ごすために必要な力のことです。
人と共に生きていくために必要不可欠な力のことですが明確な定義はないため、社会の一員として生きるうえで求められる力のことを広く一般的に社会性とよんでいます。
初めはひとり遊びをしていた子どもも、いつしかパパ、ママ、友だちと一緒に遊べるようになり、協力したり譲ったり順番を守ったりしてみんな遊びをするようになります。
身につけたさまざまな力を組み合わせて、一緒にイメージを共有したり、同じ目標に向かって挑戦したり、みんなで喜んだり悔しがったりもできるようになります。
厳しく子どもを抑えつけるより、子どもの自主性を大切に、こどもを認めるような関わりが社会性を育むことにつながりますよ。
まとめ
子どもの遊びは無意味なようにも単純なようにも見えてしまいますが、生きるうえで必要な力を築く基礎の部分であることがわかりましたね。
私たち大人ができることは子どもが安心してのびのび遊べるような安全な環境をつくることや、「やってみたい」と思えるような物の準備、必要以上の声かけをせず子どもの主体性を見守れる広い心をもつこと。
そのためにはパパ、ママの心の“あそび”も大切!
たまには息抜きをしたり、好きなことを楽しむ時間をあえてとってあげましょうね。
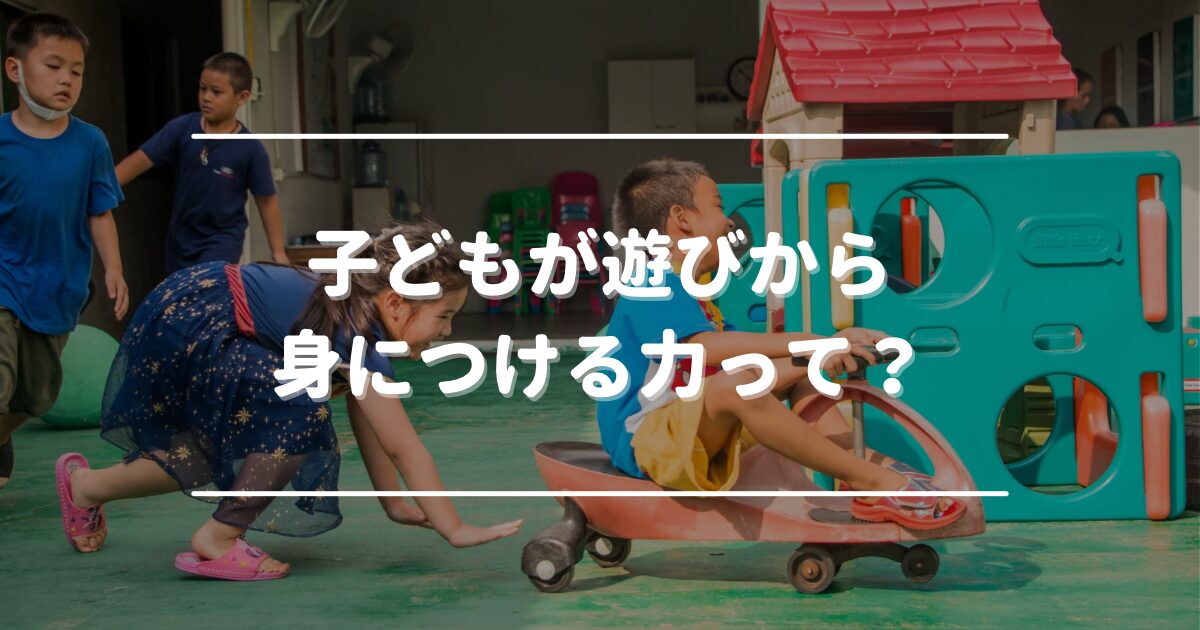
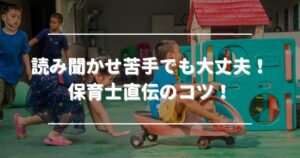
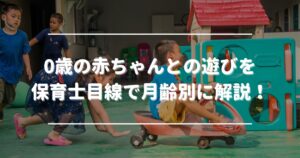

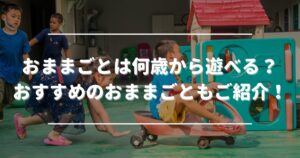
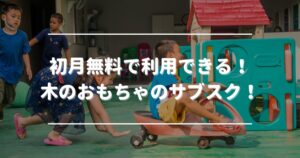
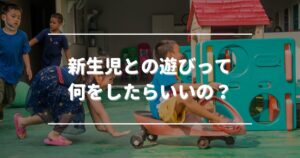
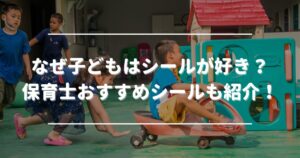

コメント